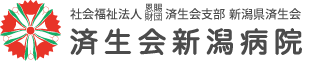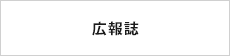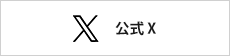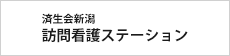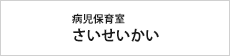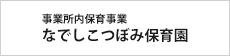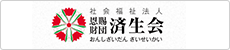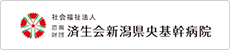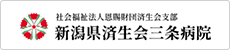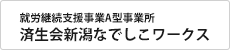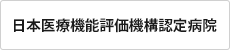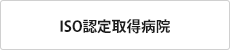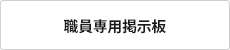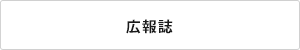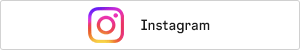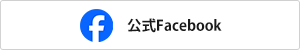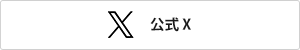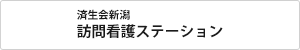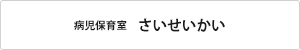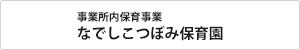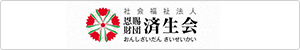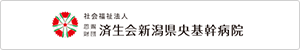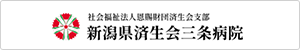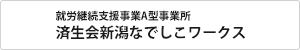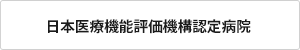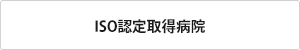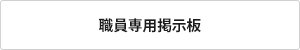栄養科-チーム医療について
NST(栄養サポートチーム)
栄養管理の流れ
全入院患者さんに対して栄養スクリーニングを行います。
栄養スクリーニングで栄養不良と判断した場合、栄養管理計画を立てて経過を観察し、定期的に評価しています。
活動の流れ
栄養スクリーニングで栄養不良と判断された場合や、主治医や病棟、褥瘡チーム、摂食嚥下チームからの依頼があった患者さんに対しNST介入検討を実施し、主治医の介入要請許可を得てチーム介入します。
週1回のカンファレンス・ラウンドを実施し、栄養のプランニング、主治医への提言等を行います。
構成メンバー
医師・歯科医師・看護師・薬剤師・管理栄養士・臨床検査技師・作業療法士・理学療法士・歯科衛生士

摂食嚥下チーム
様々な病因により、噛む・飲み込むといった食動作ができなくなった方を対象に、摂食嚥下リハビリテーションチームが介入しております。チームのメンバーは耳鼻科医師、歯科医師、歯科衛生士、看護師、作業療法士、管理栄養士で、毎週病棟回診を行っております。その中で、管理栄養士は喫食状況の把握と栄養アセスメント、食形態の選択、栄養補助食品の検討、退院時の栄養指導等を行います。
褥瘡対策チーム
週1回の褥瘡回診に医師・看護師・薬剤師らと共に管理栄養士も参加しています。
褥瘡の予防や治療には患者さんの栄養状態が関わってくるため、ベッドサイドで患者さんの状態を把握し、食事から病状の改善を促します。また、NSTとも連携し、必要に応じてNST介入要請も行います。
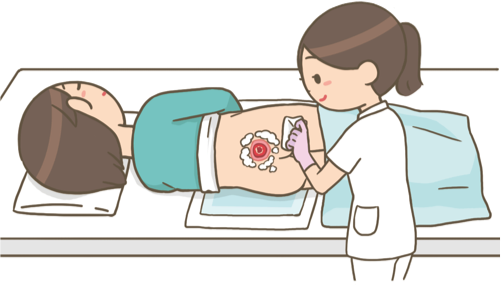
呼吸器リハビリテーションチーム
肺の病気は、肺の治療だけでなく、栄養もとても重要です。COPD(慢性閉塞性肺疾患)や肺炎、気管支喘息などの病気になると、呼吸をするために普通の人よりも多くのエネルギーを必要とします。「食事量が減る」ことで、「体重が減る」→「筋肉が減る」→「呼吸がしづらい」→「食事がつらい」という悪循環が起き、低栄養状態に陥ると病気の回復に時間がかかります。そこで、患者さまのADL(日常生活活動)やQOL(生活の質)の維持・向上と早期退院を目指して行われるのが呼吸器リハビリテーションです。医師、看護師、理学療法士、作業療法士、医療ソーシャルワーカー、管理栄養士によるチームで、患者さまの情報を共有し、必要な援助を検討しています。管理栄養士は、患者さまの栄養状態を評価し、食事相談や栄養指導を行っています。
心臓リハビリテーション
心臓リハビリテーションとは、心臓病の患者さんが、体力を回復し自信を取り戻し、快適な家庭生活や社会生活に復帰すると共に、再発や再入院を防止することを目指して行う総合的活動プログラムのことです。内容として、運動療法と学習活動・生活指導・相談(カウンセリング)などを含みます。
心臓リハビリテーション対象患者さんの栄養状態は、過栄養の結果、高血圧や糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病の患者さんと、心不全進行による低栄養の患者さんの大きく2つに分けられます。(2021年改訂版心血管疾患におけるリハビリテーションに関するガイドラインより一部改変)医師、看護師、理学療法士、作業療法士、臨床検査技師、医療ソーシャルワーカー、管理栄養士によるチームで、定期的にカンファレンスを行い、患者さんの栄養状態を評価し、個別に介入しています。