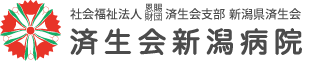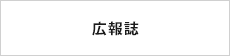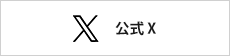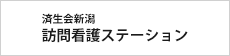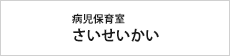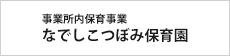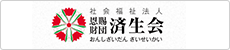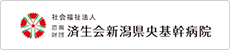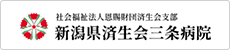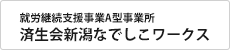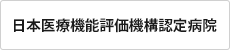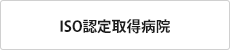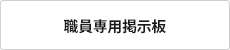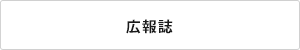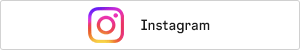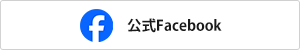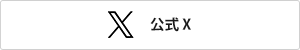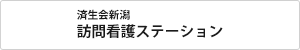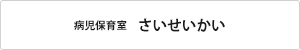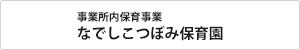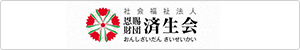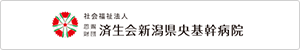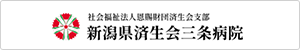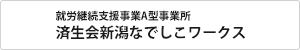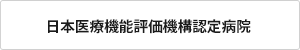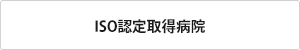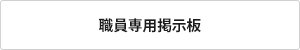なでしこCheers!11月号を、広報誌・パンフレットページに掲載しました。
ぜひご覧ください。
All posts by c15eehzg
平成28年度 初期臨床研修二次募集について
マッチング公表後の空き定員に対して、初期臨床研修医二次募集 採用試験を下記の通り行います。
平成28年度 初期臨床研修医 二次募集要項
| プログラム名 | 済生会新潟第二病院臨床研修プログラム |
|---|---|
| 試験日時 | 平成27年11月29日(日)午前中 |
| 会場 | 済生会新潟第二病院 |
| 選考方法 | 面接・小論文 |
| 対象者 | 第110回医師国家試験を受験し、平成28年度に医師免許取得予定者 |
| 申込方法 | 次の出願書類を下記申込先へ持参又は郵送(簡易書留) ・臨床研修申込書(A4) ・履歴書(A3) ・卒業証明書または卒業見込証明書 ・成績証明書 |
| 申込先 | 済生会新潟第二病院 教育研修センター 〒950-1104 新潟県新潟市西区寺地280-7 TEL:025-233-6161(内線2253) Eメール:rinken@ngt.saiseikai.or.jp |
| 出願締切日 | 平成27年11月19日(木)当日消印有効 |
人生いろいろ、コーチングもいろいろ 高次脳機能障害と向き合うこと、ピアノを教えること
報告:第234回(15‐08月)済生会新潟第二病院眼科勉強会 立神粧子
日時:平成27年8月5日(水)16:30~18:00
場所:済生会新潟第二病院眼科外来
http://andonoburo.net/on/3962
講演要約
1.高次脳機能障害とは
高次脳機能障害は脳外傷、脳卒中、脳腫瘍などを原因とする器質性の後遺障害である。とくに前頭葉の認知機能の働きに問題が生じる。認知機能とは、①覚醒と周囲への意識と心的エネルギー、②感情をコントロールする抑制と発動性、③注意と集中、④情報処理、⑤記憶、⑥遂行機能と論理的思考力、などの諸機能のこと。これらを下から順番に階層にして示しているのが「神経心理ピラミッド」の図表である。ピラミッドには最下層に“リハビリに取り組む意欲”が置かれ、最上層には“受容”と“自己構築”が置かれている。ピラミッド型が示すように下位の機能が働いていないと上位の機能はうまく機能しない。と同時に、諸機能は連動し相互に作用する。
脳損傷の特殊性として、脳細胞の欠損は身体の他の臓器と異なり再生しないことが挙げられる。しかも脳の機能はその人固有の人生の学習の記憶によって成り立っている。人それぞれ歩んできた人生が違うので、AさんとBさんとは神経回路のつながり方は全く異なる。本人に障害が残った自覚がない場合や、家族が症状の本質を理解しないために的確な支援ができない場合もある。そのため、症状自体に加え治療の目標も個々で異なり、リハビリは困難を極める。
2.Rusk研究所における脳損傷通院プログラムとは
夫は2001年の秋に重篤な解離性椎骨動脈破裂によるくも膜下出血を発症し、脳損傷(高次脳機能障害)が残存した。2004〜05の1年間、夫と筆者はNew York大学医療センター・リハビリテーション医学Rusk研究所の「脳損傷通院プログラム」で機能回復訓練を受けた。Ruskの通院プログラムは神経心理学を学問的基盤としたホリスティックなアプローチで、対人コミュニケーションを中心とした療法的プログラムである。20週を1サイクルとする訓練は個々のゴールにあわせて周到に計画され、理論と実践が巧みに組み合わされ構造化されている。訓練生は規則的な訓練の中で、症状の本質の理解と補填戦略を繰り返し学ぶことになる。
Rusk研究所での夫の訓練が終わるとき、Ben-Yishay博士から「君たちが訓練に成功したのは、君たちが成熟した音楽家で、訓練ということの意味を理解していたからだ」と言われた。このことについて考えてみたい。
3.ピアノを教えるとは
ピアノを教えるとき、専門家を育てるだけでなく、初心者、子供の情操教育、大人の趣味など、対象者は多岐にわたる。脳損傷が個々のケースで全く異なるように、年齢、習熟度、目的が一人一人異なる。ピアノを教えるということは、Ruskでの訓練と同じように、①多様なゴールを理解する、②個人の特性に合わせて(=相手の脳と心になり)指導する、③その都度ゴールを定めて、技術と考え方の両面からゴールの達成に向け訓練する、④教え込むのではなく自分でできるように導く、⑤ほめて育てる+厳しく指摘する、などを意味する。
良いピアノの指導者(=コーチ)は、①この上なく音楽を愛する、②情報交換を怠らずよく勉強する、③相手を知ろうとする、④レッスンの目的・方法論を明確にもつ、⑤渾身のレッスンをする、などの資質を持つことが望ましい。指導者は改善すべきところを見つけ、理論的かつ実践的に技術と方法を示す。生徒の側も、主体的にその道の専門家のアドバイスに耳と心を傾け、順応性をもって素直に訓練を受ける態勢になることが大切である。指導の目的は生徒が「自分で自分を改善させる」ことができるようにすること。つまり、自分の音を批評できる能力、悪いところを自分で気づき予防できる能力、様々なテクニック(戦略)を知り自分で使いこなす能力などを、訓練によって身につけさせることである。これらはそのまま高次脳機能障害のコーチングの技術に当てはまる。
4.高次脳機能障害のコーチング
脳損傷者のコーチングには重要な前提条件がある。第一に、訓練生が落ち着いていて客観的な時にのみコーチングする。イライラしていると抑制困難症を引き起こし、コーチングが逆効果となる。第二に、訓練生が疲れすぎていない時にコーチする。神経疲労を起こしていると、コーチングを受け取る集中力も情報処理力も十分に働かない。第三に、コーチされる側も活発にコーチングを求める意欲を持つ。本人に改善する意志がないと意味がない。
そして脳損傷のコーチングの原理としては、①ひとつの問題に焦点を当て,選択的であること、②問題は具体的に指摘し、慎重に戦略を選び、具体的に解決策を示す、③良いことも具体的に指摘する、④改善すべきことを良いことの指摘に挟む「サンドイッチ効果」の技法を使ってコーチする、⑤ユーモアを忘れないように、などである。
5.受信情報を確認しながら会話しよう
例えば、会話の訓練がある。隣の人と会話をしてみよう。その際に、受信情報を確認する〈確認の技〉や、相手の言葉を借りる〈語幹どりの技〉などを使ってみると、発動性のない人も、抑制困難な人も、それぞれの問題にとって助けになる戦略を用いて会話を進める事ができる。戦略を使うことで発動性のない人には発話のきっかけとなり、抑制困難症の人には話の筋道からそれないようにすることができる。
会話の訓練以外にも、何か動作を覚える時の確認の手順や、日常生活を構造化することで動きの流れを作っていくことなど、症状に合わせてそれぞれの戦略を用いて一歩先のゴールを設定して地道に訓練することで、日常生活をよりスムーズにする事ができる。障害の完治は期待できないが、訓練により戦略を用いる技術を習慣化する事はできる。
6.コーチングの意義
脳損傷者がこうした技術を身につける事ができれば、家族や周囲の人たちとの共同生活の中でも、自分の存在に価値がある事を自ら感じる事ができる。コーチングの技術、コーチを求める順応性のある心と意欲が双方に求められる。ケアマネージャーやヘルパーさんたちとの連携も必要である。最終的には、自分で自分を改善できる力を持ち、相手との良い関係を再構築できるようにしたい。コーチする人もコーチされる人も、その時の問題にひとつずつ取り組み、落ち着いて訓練してつねに改善することが肝要である。
音楽の訓練を通じて「訓練」や「技術の獲得」ということの本質を理解していた我々だったので、Ben-Yishay博士は「訓練は成功した」と言及したのだろう。それほど、脳損傷者にとって自分の症状を理解し、それに対する戦略の習得から習慣化に至る地道な繰り返しの訓練が必要、ということである。
略 歴
1981年 東京芸術大学音楽学部卒業
1984年 国際ロータリー財団奨学生として渡米
1988年 シカゴ大学大学院修了(芸術学修士号)
1991年 南カリフォルニア大学大学院修了(音楽芸術学博士号)
2004-05年 NY大学医療センターRusk研究所 脳損傷者の通院プログラム参加
治療体験記を『総合リハビリテーション』(医学書院)に連載(2006年)
2010年 『前頭葉機能不全その先の戦略』(医学書院)
現在:フェリス女学院大学音楽学部音楽芸術学科教授、音楽学部長、日本ピアノ教育連盟評議員、米国Pi Kappa Lambda会員。
著 書
『前頭葉機能不全/その先の戦略:Rusk通院プログラムと神経心理ピラミッド』
立神粧子著 (2010年11月 医学書院)
医学書院のHPに以下のように紹介されている。
「高次脳機能障害の機能回復訓練プログラムであるニューヨーク大学の『Rusk研究所脳損傷通院プログラム』。全人的アプローチを旨とする本プログラムは世界的に著名だが、これまで訓練の詳細は不透明なままであった。本書はプログラムを実体験し、劇的に症状が改善した脳損傷者の家族による治療体験を余すことなく紹介。脳損傷リハビリテーション医療に携わる全関係者必読の書」
http://www.igaku-shoin.co.jp/bookDetail.do?book=62912
後 記
素晴らしい講演でした。ご夫婦で東京芸大出身の音楽家。立神先生はピアノ、ご主人はトランペット。ヤマハ楽器にお勤めだったご主人が「くも膜下出血」を発症。その克服にご夫婦で立ち向かい、ニューヨークで約一年の研修を受け、その後も地道な訓練をひたすらに続け、生活を取り戻した(今でも進行形)壮絶なお話。訓練と戦略のおかげで、絶望的だった夫との生活は奇跡的に改善され、希望が持てる人生を歩みだすことができた。後半ではご主人のユーモア溢れる講演もお聞きした。
こうした経験から立神先生は、神経心理ピラミッドに則った訓練は、脳損傷リハビリにもピアノ教育にも有効なツールとなっていることに気が付いたという。すべてのリハビリあるいは習い事のいいお手本となるお話を、感動と共に拝聴しました。
立神先生ご夫婦の健やかなお暮しを祈念致します。この度は、誠にありがとうございました。
新潟盲学校弁論大会 イン 済生会
報告:第233回(15-07)済生会新潟第二病院眼科勉強会 盲学校弁論大会
日時:平成27年7月8日(水)16:30~17:30
場所:済生会新潟第二病院 眼科外来
(1)「僕の父」 中学部3年
(2)「夢は地道にコツコツと」 高等部普通科3年
http://andonoburo.net/on/3807
(1)「僕の父」新潟県立新潟盲学校 中学部3年
僕は、月曜日から木曜日まで寄宿舎に泊まります。中学部になってから、父と毎日会えません。だから少し淋しいです。
僕の父はやさしいです。休みのときは父と一緒にお風呂に入ります。僕の身体をごしごし洗ってくれます。そんなときは、「お前、小さいときよく泣いてたな。お父ちゃんのくしゃみや鼻かむ音で泣いてたな」と僕の子供の頃の話をしてくれます。
また、 「お出かけについて」話をします。お出かけに連れて行ってくれます。僕の好きな巫女爺や熱気球大会や花火大会を見に行ったり、いろいろな所に連れて行ってくれます。今年のゴールデンウィークは、毎日、柏崎や長岡に連れて行ってもらいました。行事のときは、家族みんなを学校まで送ってくれます。体育祭のときは「がんばれ、がんばれ」と応援してくれました。
文化祭では作業で作ったフォトフレームをよくできた」と言ったり、有志のステージ発表で、僕たちがよさこいソーランを踊ったときは、「上手だったよ。」と、ほめてくれたりしました。
僕とよく遊んでくれます。総合体育館に行って、僕の手を引いて走ります。そのとき父は飛ばします。速いので僕が手を離しそうになると、「おい、お前なにしてやんだ。」と言います。
家ではWiiでゲームをしてくれます。座禅やスキーのジャンプのゲームを教えてくれます。父は、「飛べ!飛べ!前、前、前、前・・・」と、ジャンプのタイミングを指示してくれます。僕が上手に飛べると、「123メートルだって。いったねえ。」と、ほめてくれます。テレビで「お宝鑑定団」やニュースをよく見ています。
父は電気工事士をしています。仕事に出かけるとき僕に「よし、お父ちゃん仕事に行ってきますよ」と言って出かけます。そんな父はかっこいいと思います。
僕は父が一番大好きです。これからも元気でいて下さい。お父さん。
(2)「夢は地道にコツコツと」新潟県立新潟盲学校 高等部普通科3年
今から話しをするのは、二年間話すことが出来なかった中学校の時の話です。
私は、生まれつきの弱視ですが、勇気が出せず、本当に信用している友達にしか目が悪いことを打ち明けていませんでした。だから私は他の友達に気づかれないように学校生活を送っていました。高校受験も、盲学校進学ではなく、普通校進学を希望していました。なぜなら私は、盲学校は目が全く見えない人が通うところだと勘違いしており、盲学校に進学することで、目が悪いことがみんなに知られてしまうのを恐れたからです。
私は、普通校合格のために必死に勉強しました。入試当日、教室に書見台が用意され、拡大された答案用紙が配られました。他の受験生たちがじろじろと見ているのがとても恥ずかしかったし、視線を怖く感じました。それでも、入試を出来る限りがんばりました。休み時間には友達が面白い話や、「俺だめだった」みたいな話をして私を勇気づけてくれました。志望した高校には、友達が多く受験していたので、緊張せずに取り組めました。入試が終わったあと、『やることはやった!がんばった!』という達成感よりも、『無事に高校に入学できるか』という不安でいっぱいでした。
志望校合格発表の日。自分の受験番号を一生懸命探しました。1、2、3、4……数が近づいてくるにつれ、私の心臓はバクバクしました。結果は不合格でした。私は、頭が真っ白になりました。理解できずに何度も何度も探しましたが、番号はありませんでした。
私は、二次の新潟盲学校受験を頑張ろうと思い、再び努力しました。そして、新潟盲学校に合格しました。うれしいのですが、素直に喜べませんでした。目が見えない人がいく学校で、自分の目が悪いことを知られてしまうと思ったからです。友達に「どこ入学するの?」と聞かれて盲学校と答えるのが嫌でした。私の不安は無事に入学できるかというものから、盲学校ってどんなところなのかというものに変わってい
き、入学式が近づくにつれてその不安がどんどん大きくなりました。ついには盲学校入学が決まっているのに、「普通校に行きたい」「普通校で勉強したい」とさえ思ってしまいました。
しかし、その不安は入学式で生徒会長からのお祝いの言葉を聞いたときに全て吹き飛びました。しっかりハキハキと言っている姿を見て「本当に目が悪いのか?」と思いました。学校生活が始まり、グランドソフトボール部の先輩たちがアイマスクをしていても、普通に投げたり打ったり、走ったりしているのを見て「すごいなぁ」と思いました。さらに、寄宿舎でも私よりもよっぽど小さな子が一人暮らしをしていてすごいと思いました。
盲学校に来たばかりで何も知らなかった私に気軽に話してくれる人ばかりでした。私のことを大好きと言ってくれる人もいました。私は、とてもうれしかったです。私は、『盲学校入学は、間違いじゃなかったんだ、もし私が普通校に合格していたら、こんなすてきな友達と出会えなかったし、私のことをわかってくれる先生方もいなかった!普通校に落ちたから今の私がある!』と思っています。
三年生になり、たくさんの友達といつもわいわいしながら学校生活を送っています。そんな私には今、夢があります。それは、パン屋になるという夢です。私がパン屋を意識したのは、中三の時です。「焼きたてジャパン」というテレビアニメにハマり、家でパンを作り始めたのがきっかけです。目盛りやはかりの線が見えにくい私にとって、非常に難しい夢だと思います。しかし、その夢をあきらめたくはありません。なぜなら、私はパンが好きだからです。
私は、二年生の時から「産業社会と人間」という授業を選択しています。その授業では、日頃のあいさつ、礼儀、作業など就職に関したことを学んでいます。慣れてくると現場実習があり、二週間の現場実習を行いました。金具組み立てや段ボール作りなどを一日六時間以上やるので、とてもくたくたになりましたが、この実習を通して仕事の大変さや辛さがしみじみとわかりました。今年も七月にまた実習があります。就職に向けて大変な実習もがんばっていきたいです。
さて、みなさんは、連続テレビ小説「まれ」を知っていますか?夢が嫌いなまれが言った言葉に「人生は地道にコツコツ」という言葉があります。まれは夢が嫌いですが、私は夢が大好きです。夢がなかったら人生は楽しくないし、夢が無いと何事もがんばれないと思います。みなさんも夢に向かって地道にコツコツとがんばりましょう。たとえ大きな障害があり、それがどんなに暗闇に包まれたとしても、続けていれば必ず夢に近づいて行くはずです。私もパン屋という夢に向かって走り続けていきます。
これで発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。
後記
済生会新潟第二病院眼科勉強会の七月は、毎年新潟盲学校の生徒による弁論大会を行っています。盲学校生が胸に秘めた熱い思いを弁論は、毎回好評です。
今回も二人の弁士は、一所懸命に時に身振りを交えて弁論してくれました。参加者からも多くの賛辞が寄せられ、感動の弁論大会でした。
@全国盲学校弁論大会弁論47話「生きるということ―鎖の輪が広がる―」
http://www.kyoikushinsha.co.jp/book/0103/index.html
平成20年度で77回目を迎えた全国盲学校弁論大会の発表作品は、“こころ”の課題を抱える現代の児童生徒、学生にインパクトとともに大きな勇気を与えている。学校、家庭での読み聞かせにお勧めの一冊。
我が国の視覚障害者のリハビリテーションの歴史
報告:第232回(15‐06月)済生会新潟第二病院眼科勉強会 吉野由美子
演題:「我が国の視覚障害者のリハビリテーションの歴史」
講師:吉野 由美子(視覚障害リハビリテーション協会)
日時:平成27年06月03日(水)16:30 ~ 18:00
場所:済生会新潟第二病院 眼科外来
http://andonoburo.net/on/3717
講演要約
はじめに
リハビリテーションという言葉の定義は、元々がキリスト教における「波紋を解き、身分を回復する」という意味から派生して「再び相応しい状態に戻す」という意味から、人生の半ばで何らかの障害を負った方たちに対して、生活や社会活動において失われた機能を回復させるための様々なサービスを表す言葉となった。しかし、私がここでお話しする視覚障害者に対するリハビリテーションは、幼い頃からの視覚障害者や中途視覚障害者等すべての方たちの生活を向上させるためにおこなわれている医療・福祉・教育に関わる広範囲なサービスについての我が国における歴史的展開についてである。
1.特殊コミュニティーから盲学校を中心としたコミュニティーへ
9世紀頃視覚障害者は、琵琶法師として、また歌舞音曲を行う者として細々と生計を立てており、その技術を伝え自らを守るために、当道座という独特の組織を成立した。江戸時代になると、杉山検校とその弟子たちが、梁・灸等の技術を確立し、その治療で将軍の病気を治したことなどが認められて、検校を頂点とする独特の階級社会を作り上げ、「あ・は・き業」の独占をはじめ、様々な特権を得た。
この特権は、明治維新と共に、1871年当道座の解体と共に廃止されることとなり、視覚障害者は、「あ・は・き」等の今まで培ってきた知識を次世代に伝える手段を失った。そこで、盲学校設立の運動が巻き起こり、1878年には京都盲唖学院が開設され、1880年に石川倉治によって開発された日本式点字を使った教育法と共に、全国に広まった。
2.戦争と傷痍軍人と中途視覚障害者のリハビリテーションの芽生え
日清・日露戦争後の傷痍軍人対策として、障害を持った者に対する機能回復訓練や職業訓練という考え方が我が国にも芽生えた。視覚障害者に特化した施設としては、岩橋武雄らの提唱により1938年に設立された「失明軍人寮」が最初である。
傷痍軍人対策としてのリハビリテーションは、敗戦後占領軍により排除されたが、そこで培われた方法・技術は受け継がれ、国立リハビリテーションセンター、塩原視力障害者センターなど、各地に中途視覚障害者のリハ施設が開設された。
また、1948年に、ヘレンケラーの二度目の来日を機に日本盲人会連合(日盲連)が結成され、視覚障害者の生活向上に向けての様々な運動が開花した。
3.目標は経済的自立、単独視覚障害者を対象、収容型中心の視覚リハの時代
1949年に成立した身体障害者福祉法の目的は、「障害者が経済的に自立し、社会に貢献する」ことを目指したサービスを制度化することであった。そのため、視覚障害者に対するリハは、三療業(あ・は・き)を中心とする職業訓練で、幼い頃からの視覚障害者については、盲学校で、中途視覚障害者に対しては、国立視力障害者センターを中心に収容型施設で行われた。訓練しても経済的自立が望めない、視覚と他の障害を合わせ持つ人や、主婦層や高齢の方に対する生活訓練などは、初期の頃は対象外とされた。
1970年に日本ライトハウスにおいて歩行訓練士養成講習会が行われたのが、我が国における視覚リハ専門家の養成という意味では初めてのことで、その後、1990年に国リハ学院に「視覚障害生活訓練専門職員養成課程」が開設されたが、視覚リハの専門職員養成は、福祉の側からの働きかけによって行われ、肢体障害者のリハに携わる理学療法士等が医療の要請の中から生まれたこととは大きく異なっており、その後の視覚リハの展開において大きな影響を与えた。
4.制度と対象の激変時代
1980年から始まった国際障害者年やノーマライゼーション思想の我が国への浸透を経て、障害者リハの目標は、経済的自立から社会への参加を目指すものに変化し、在宅による訓練も少しずつ開始されたが、基本的には大きな変化はなかった。しかし、2005年に成立した障害者自立支援法は、身体・知的・精神と言う3障害を同一施設でサービス対象とすることと、作業や訓練を行う施設と生活や介護を行う施設とを大きく区分すると言うことが打ち出され、サービス体制が激変した。
また視覚障害の原因の激変により、幼い頃からの視覚障害者が減り、中途障害者が増加、また、60歳以上の視覚障害者が視覚障害者全体の70%を占める事態となった。
2014年に、我が国は障害者の権利に関する条約を批准、リハビリテーションは、誰でも、どこに住んでいても、性別や年齢に関わりなく、受傷後できるだけ早期に受ける権利を障害者が有し、国はその権利を実現するための環境を整える義務を負うこととなり、現在視覚リハサービスの体型を見直さざるを得ないと言う激変期にいたっている。
5.まとめ
概括してきたように、我が国の視覚障害リハにおいては、幼い頃からの視覚障害者が中心となり生活のために作ってきた特殊コミュニティ-と、そのもとで育まれた「あ・は・き」と言う職業等を中心として展開されてきた。しかしながら、視覚障害となる原因の激変、制度の激変、高齢視覚障害者の急速な増加により、単独視覚障害者中心の教育や職業訓練を中心とする体制は維持できなくなってきている。
このことを踏まえ、広く一般社会への啓発と制度サービス体制の見直しが必要な時期が今まさにきているのである。
プロフィール
1947年 東京生まれ 67歳
1968年 東京教育大学(現筑波大学)付属盲学校高等部普通科卒業
1974年 日本福祉大社会福祉学部卒業後、名古屋ライトハウスあけの星声の図書館に中途視覚障害者の相談業務担当として就職(初めて中途視覚障害者と出会う)
1991年 日本女子大学大学院文学研究科社会福祉専攻終了(社会学修士) 東京都立大学人文学部社会福祉学科助手
1999年4月から2009年3月まで高知女子大学社会福祉学部講師→准教授 高知女子大学在任中、高知県で視覚障害リハビリテーションの普及活動を行う。
2009年4月より任意団体視覚障害リハビリテーション協会長(現在に至る)
後記
素晴らしい講演でした。視覚障害と肢体障害の重複障害をお持ちの当事者個人の視点と、視覚障害リハビリテーション協会会長としての視点から、「我が国の視覚障害者のリハビリテーションの歴史」を語って頂きました。
視覚障害者に対するリハビリテーションというものを、先天性視覚障害者や中途視覚障害者等すべての方たちの生活を向上させるためにおこなわれている医療・福祉・教育に関わる広範囲なサービスと捉え、我が国におけるその歴史的展開について言及しました。
今後の我が国の視覚障害者に対するサービスの未来を考える時の一つの問題提起としてお聞きしました。吉野先生の益々のご活躍を祈念致します。
平成27年度インフルエンザ予防接種のご案内
平成28年度なでしこつぼみ保育園入園申込受付
平成28年度なでしこつぼみ保育園の申込受付を10月1日より開始します。
保育園のご案内はこちらをご覧ください。
受付期間
平成27年10月1日(木)から、平成27年10月30日(金)まで
※土・日・祝日を除く
※病院診察日のみ
受付時間
平日:午前8時30分から午後5時まで
受付場所
当院総務課(2階事務室内)
受付対象者
平成28年4月1日時点で、新潟市に住民票のある方
(平成28年4月1日時点での住民票登録予定者を含む)
平成28年4月1日時点で、市外に住民票登録のある方は、住票のある市町村の保育園担当課でご相談ください。
※9月14日(月)より、受付場所にて必要書類の配布を開始します。
院内保育所・病児保育棟備品見積もりに関する質問回答を掲載いたしました
検診センター休診のお知らせ
学会等による医師不在のため、下記のとおり、検診センターを休診といたします。
人間ドック、各種検診、ご予約、検便等の提出はできませんので、あらかじめご了承ください。
平成27年9月24日(木)〜 9月25日(金)
なでしこCheers!9月号を掲載しました
なでしこCheers!9月号を、広報誌・パンフレットページに掲載しました。
ぜひご覧ください。