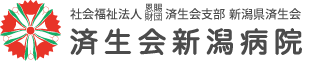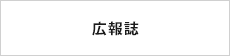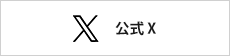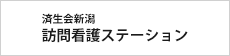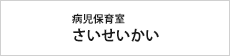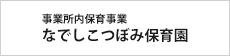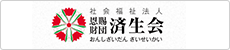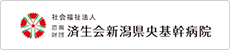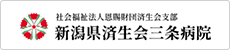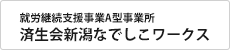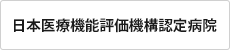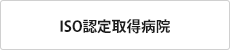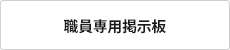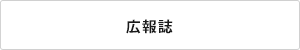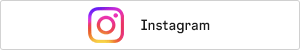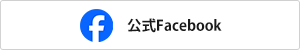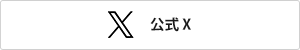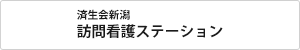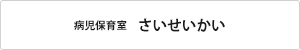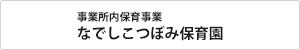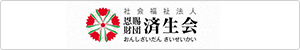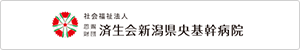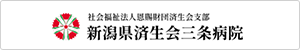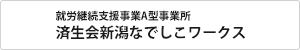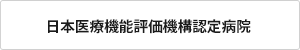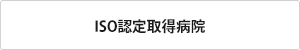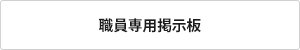なでしこCheers!5月号を、広報誌・パンフレットページに掲載しました。
ぜひご覧ください。
All posts by c15eehzg
テナント入替に伴う工事のお知らせ
標記の件につきまして、下記日程で2階テナントエリアにて工事を行います。工事中は騒音・振動等の発生によりご迷惑をお掛け致しますが、ご理解の上、ご協力の程宜しくお願い致します。
【期間】平成27年5月31日 〜 平成27年6月30日まで
※工事期間の対応等については「テナント入替スケジュール」をご確認下さい。
知る・学ぶ、そしてユーモアを忘れずに挑戦していくことの大切さ
報告:第230回(15‐04月)済生会新潟第二病院眼科勉強会 阿部直子
報告:第230回(15‐04月)済生会新潟第二病院眼科勉強会 阿部直子
演題:知る・学ぶ、そしてユーモアを忘れずに挑戦していくことの大切さ―「慢性眼科患者」の経験から私が学んだこと―
講師:阿部直子(アイサポート仙台 主任相談員/社会福祉士)
日時:平成27年4月8日(水)16:30~18:00
場所:済生会新潟第二病院眼科外来
http://andonoburo.net/on/3559
講演要約
両目のまぶたに先天的な症状を持って生まれた私は、生後まもなくの頃から眼科とのおつきあいが始まりました。以来、40数年経った今も年数回の眼科受診を続けながら日常生活を送っています。
紆余曲折の末に辿り着いた大学院教育学研究科で学んだことが活かせる職種の職員募集が仙台市の市政だよりに載っていることを私に教えてくれた教官のおかげで、大学院修了後はさまざまな障害を持つ方の生活相談支援を担う部署に相談員として就職しました。人よりけっこう遅い「社会人1年生」のスタートを切ったことになります。そして、たまたま同じ時期に始まった仙台市の地域リハビリテーションモデル事業で視覚障害者支援に関するプロジェクトのいわば「現場スタッフ」の仕事も担当させていただくことになりました。このモデル事業が基盤となって仙台市中途視覚障害者支援センターが仙台市単独事業として2005年に始まりました。今年(2015年)の春でちょうど10周年です。
支援センターでのもっとも中心となる業務は相談です。視覚障害を持つ方やその家族などから寄せられる相談に応じ、情報提供したり、福祉サービスの利用を円滑に受けられるようにするために福祉事務所等での手続きを支援したり、あるいは経済的な基盤を確保するために障害年金の請求手続きに必要な書類集めのサポートをしたり、病気や症状への適応の過程で生じる心理的葛藤につきあったり、見えない・見えにくい状況で生活する上でのちょっとした工夫(感覚の活用、道具の活用など)を助言したり……と、その内容はさまざまです。市民(視覚障害を持つ人ご本人や家族)から直接連絡をいただく以外にも、例えば病院の眼科や糖尿病内科などに勤務する医師や看護師から入院中の患者さんのことで支援協力の依頼が入り、病棟を訪問して本人・家族とお会いし、退院して後の自宅での生活再開に向けて必要な情報を提供したり手続きを支援したりすることもおこなっています。
お互いになかなか出会う機会がなく、それゆえ、ともすると孤立しがちな中途視覚障害者やその家族を主な対象とした「目の不自由な方と家族の交流会」を毎月1回開催しています。さらに、支援者どうしが分野や組織の枠を超えて交流し、お互いの専門分野を話題提供して学びあったり人脈づくりをしたりすることを目的として2000年の夏に始まった「仙台ロービジョン勉強会」の事務局役割を2006年から引き受け、こちらも毎月1回開催しています。
このようにさまざまな視覚障害者の生活設計・生活再建、あるいは眼科の患者さんやその家族が直面する心の動揺や葛藤を整理していく過程にソーシャルワーカーとして直接・間接にかかわる現在の業務を個人的なライフヒストリーを交えながら振り返ってみた時、「自分の体験だけでモノゴトのすべてを考えてはいけない」と思いつつも、ものごころつく頃からの眼科での患児・患者としての経験から得たこと、社会全体からみればマイノリティ(少数者)であるロービジョンの状態で育ち生活してきた体験から学んだことが今の私に少なからぬ影響を与えていると気づかされます。
私の場合、「低い視機能(ロービジョン)のために生じる『見える・見えないを行ったり来たり』とどうつきあうか?」という要素と、「義眼の管理や人工涙液の頻回点眼、痛みや疲れの軽減対策など、いわば『目の内部障害』とどうつきあうか?」という要素に整理されるのではないか、と自分の状況をとらえています。そして、「症状の変化(進行)に対して、心理的に、あるいは具体的な行動技術や道具の活用の工夫などによってどのように適応していくか?」を考えなければいけない場面に直面した時、しんどかったりつらかったりすることがないわけではない、というのが正直な状況です。
しかし、小児眼科(こども病院)時代に患児として眺めた医師をはじめとする多様なかかわり手どうしの連携と役割分担の姿や、国際障害者年(1981年)の1年間にテレビや映画で接した、国内・海外に暮らすさまざまな障害者が自身の障害とつきあいながらも社会の中でいきいきとその人・その人の役割を果たしている/果たそうとしている姿から学んだことは現在、私にとって「思考の基本・お手本」としてとくに強い影響を与えているように思います。
そんな慢性眼科患者としての生活過程を振り返ってみて、疾患(やそのために生じる機能低下・喪失)とよりよくつきあいながら暮らしていくうえで重要なことを考えてみました。
(1)「私もあんなふうになりたい」「なれるかも…」と思えるような良き手本となる人の行動・生きざまに触れることによって気持ちの上で強くなれるように思います。
(2)世界の多様な多民族・多文化事情やマイノリティ事情、弱さに起因する社会問題を知ることによって、疾患や障害のために直面する課題を客観的・相対的にとらえる視点を育むことができるように思います。
(3)失敗や挫折、困難や苦労を「何事も経験」ととらえ直すことによって、心の余裕が生まれるように思います。
(4)教育の力・笑いの力は困難な状況をのりきっていくうえで重要ではないでしょうか。
略歴
兵庫県出身。関西と関東を行き来しながら子ども時代を過ごす。
1995年 同志社大学文学部文化史学専攻卒業
2001年 東北大学大学院教育学研究科教育心理学専攻修士課程修了
2001年 (財)仙台市身体障害者福祉協会に仙台市太白障害者生活支援センター相談員として入職。この間、仙台市地域リハビリテーションモデル事業運営協議会ワーキンググループ委員(2002年~2004年)、中途視覚障害者への地域リハビリテーションシステム研究事業ワーキンググループ委員(2004年~2005年)を経験。
2005年 視覚障害者を支援する会(現在のNPO法人アイサポート仙台)に仙台市中途視覚障害者支援センター相談員として入職
@NPO法人アイサポート仙台
http://www15.plala.or.jp/isupport/
後記
阿部直子さんは、魅力いっぱいな素敵な女性でした。アイサポート仙台は、相談も患者さんのみでなく、医師や医療関係者が訪れるというのはビックリでした。行政と対決するのでなく、味方につけての活動は、時として制約もあろうかと思いますが、ことをなす王道です。今年創立10周年を迎えたということですが、色々な職種の方々が集ってここまで続けてこられたのは素晴らしいものです。「中途視覚障害者交流会」(毎月)、「仙台ロービジョン勉強会」(毎月)も充実しているようです。
「慢性眼科患者」としてのライフヒストリーでは、ご自身の障害のことをカミングアウトして頂きました。医師は病気の診断と治療を行いますが、生活上のご苦労はあまり知りません。貴重なお話を伺いました。最後に強調された、知る・学ぶ、ユーモアを忘れずに挑戦していくというくだりは、納得して聞くことが出来ました。阿部先生のお話をお聞きして、改めて魅力をいくつも発見しました。参加者から「軽い語りかけで救われる」という感想もありましたが、明るい語り口は魅力です。ご両親の愛情をたっぷりと受けて育ったのだろうと感じました。
蛇足になりますが、我が国におけるロービジョンケアの先駆者として、弱視学級設立に尽力した小柳美三東北大眼科教授(初代)が、日本眼科学会創立100周年記念誌に紹介されています。「1929年に小柳美三東北大眼科教授がLV児の特殊教育の必要性を訴え、1933年に南山尋常小学校(東京麻布)に全国初の弱視学級が開設された。」
加えて、東大眼科の原田政美先生が、1965年に東北大学教育学部教育心理学科の視覚欠陥学講座に教授として赴任し、視覚障害リハビリテーションに尽力されています。こうしたことから「仙台が日本のロービジョンケア発祥の地なのでは?」という思いを強くしています。
このような背景を知ると、阿部先生が作り上げてきたアイサポート仙台は、偶然ではないという思いがします。創立10年を迎え、これからますます飛躍の時だと思います。今後の活躍を祈念しています。
視覚障害者の求めた“豊かな自己実現”―その基盤となった教育―
報告:第229回(15‐03月)済生会新潟第二病院 眼科勉強会 岸 博実
報告:第229回(15‐03月)済生会新潟第二病院 眼科勉強会 岸 博実
演題:「視覚障害者の求めた“豊かな自己実現”―その基盤となった教育―」
講師:岸 博実(京都府立盲学校教諭・日本盲教育史研究会事務局長:注1)
日時:平成27年03月11日(水)16:30 ~ 18:00
場所:済生会新潟第二病院 眼科外来
http://andonoburo.net/on/3508
講演要約
Ⅰ 琵琶法師・按摩師~「見えない歴史や見えない体内」を記憶と手の力で
古来日本の盲人は、「見えない歴史や見えない体内」を記憶と手の力で操作し、琵琶法師や按摩師などの業を獲得して来ました。江戸時代、当道座(注2)が自治権を認められ、幕府に重用される盲人も現れました。1682年(天和2)、盲人に鍼を教える学校「杉山流鍼治導引稽古所」(注3)も開設しました。バランタン・アユイが、世界最初の盲学校であるパリ青年訓盲院を設立した1784年よりも100年以上早かったのです。
Ⅱ 明治政府の施策
明治政府は長年続いた当道座を廃止します。状況を打開する第一着手は教育でした。1878年(明治11)京都盲唖院発足、2年後、東京楽善会訓盲院も授業開始。京都の古河太四郎は「自己食力」を構想し、楽善会はその基調に自助論を据えていました。いずれも古い徒弟教育を否定し、普通教育の上に職業教育を築きました。中村正直(注4)の「天は自ら助くる者を助く」論は自我形成と生存競争、二つの課題を盲人に課しました。
Ⅲ 初期の日本盲教育
京都も東京も、点字がない現実から始まりました。木に刻んだ文字、紙を用いた凸字、紙にカナカナをプレスしたイソップ物語、鍼理論を漢字・仮名交じりに成形した凸文字教科書などが作られました。墨字の書き方の練習もしました。しかし、明治10年代の盲生にとって学習は著しく困難でした。退学が相次ぎました。
Ⅳ 点字の登場
事態を根本から変えていくのが点字です。人類の文字は凹字から始まりましたが、紙の発明によって平らな字に変わり盲人が読み書きし難くなりました。盲字用凸字から12点点字に飛躍し、ルイ・ブライユが6点方式に改革したことを通じて、世界の盲人にとって自由に読み書きできる文字が獲得されました(注5)。私は、アーミテージの「盲人に対する最善なるものの唯一の審判者は盲人」という提言も重要であったと考えています。
わが国では、英国の盲人アーミテージによる『盲人の教育と職業』という書籍がそれを持ち帰った手島精一から小西信八東京盲唖学校長の手に渡り、石川倉次の点字研究が始まります。その出発点で、高田出身の小林新吉少年がアルファベット点字の読み書きを円滑に行ったことが決定的な駆動力となりました。
Ⅴ 小西信八の功績
明治期後半からの盲教育においては、東京盲唖学校長・小西信八の認識がもたらした影響が重要です。彼は1896年(明治29)から1898年(明治31)にかけて、欧米の障害児教育を視察しました。国家による教育を受ける権利が、盲児、聾唖児にもある(「天賦人権論」に立った認識であったかどうかは吟味を要しますが)と、はっきり主張しました。
1906年(明治39)聾唖教育全国大会 3校長(小西信八・古河太四郎・鳥居嘉三郎)の「文部大臣建言」『上申書』・・・盲ト聾トハ全ク性情ヲ異ニシ盲者ノ為ニ考慮ヲ尽シタル成案モ之ヲ聾者ニ適用スベカラズ聾者ノ為ニ工夫ヲ凝ラシタル良案モ之ヲ盲者ニ利用ス可カラズ・・・・
Ⅵ 盲・聾 教育の義務化と分離
明治から戦時中にかけて続けられた帝国盲教育会などによる運動の結果、盲・聾教育の義務化と分離は、1947年(昭和22)教育基本法、学校教育法によって果たされました。最後に盲・唖分離が行われたのは石川県で、それは1965年(昭和40)でした。特別支援教育制度の下、今後の視覚障害教育はどのような方向に向かうのか、気にかかっています。
Ⅶ 日本盲人会
1906年(明治39)には日本盲人会も結成されました。東京と京都の教員とその教え子たちが呼びかけ人に名を連ねました。メンバーの一人、左近允孝之進は点字新聞「あけぼの」を創刊し、『盲人点字独習書』という書物も発行しています。文部省が『日本訓盲点字説明』を出すより6年も早く当事者である左近允がこの仕事をしたのです。
Ⅷ 同窓会
それらに先立って、同窓会作りが1902・3年(明治35、6)に東京でも京都でも始まり、全国の盲唖学校へと広がって行きます。自らの団体を結成して歴史を一歩前に進めようという動きの基盤になったことは間違いないと考えられます。京都府立盲学校の同窓会は、昭和の初めに国産第1号として点字タイプライターを製造・販売しました。点字盤も「京盲同製」と彫り込んで販売しました。状況に対応して生きるだけでなく、状況を変える主体者として、当事者集団が立ち現れてきたことの意義は大きかったと思われます。木下和三郎の盲人歩行論にももっと注目すべきでしょう。
自己実現を求め続ける「主体」が形成・確立されてきた過程を掘り起し、公助の範囲を縮小していくかのような今日の流れを超える力はどこから生まれてくるのかを考察したいと思っております。
==========================
注1)「日本盲教育史研究会」
2012年10月13日発足。全国各地方・学校などに埋もれている史料の発掘、保存、活用を追求し、調査・研究の成果を交流・共有。日本の明治期以降の歴史を研究することにより、今後の盲教育の方向を示唆することを企図して有志により作られた。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
「日本盲教育史研究会公式サイト」
注2)「当道座」
江戸時代に幕府から承認された視覚障害者の組織(西洋諸国のギルドにあたる)。自治権が与えられ、検校・別当、勾当、座頭の位があり、さらに細かく全部で73階級に分かれていた。当時3000人くらいがこの組織に属していた。
注3)「杉山流鍼治導引稽古所」
小川町邸の後、本所一つ目弁財天社内に開設(江戸時代後期より本社二の鳥居の手前、南側に四間余り五間の教育施設)。 この場所は、杉山和一が徳川綱吉から拝領した。現在江島杉山神社(東京都墨田区)。1682年(天和2)9月18日、家塾を改め杉山流鍼治導引稽古所を設立。アユイによる視覚障害者教育(パリ・1784年)より100年以上前のこと、世界の教育史上特筆すべき初の盲人教育である。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
「杉山流鍼治講習所」
注4)「中村正直」 1832年〈天保3年〉- 1891年〈明治24 年〉
西国立志編(自助論)~1870年(明治3年)11月9日に、サミュエル・スマイルズの『Self Help』を『西国立志篇』の邦題(別訳名『自助論』)で出版、100万部以上を売り上げ、福澤諭吉の『学問のすすめ』と並ぶ大ベストセラーとなる。自助論の序文にある‘Heaven helps those who help themselves’を「天は自ら助くる者を助く」と訳した。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
「中村正直 | 近代日本人の肖像 – 国立国会図書館」
「中村正直 – Wikipedia – ウィキペディア」
注5)「ルイ・ブライユ Louis Braille」 1809年~1852年
アルファベット6点式点字の開発者
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
「ルイ・ブライユ – Wikipedia – ウィキペディア」
==========================
追補
1.小西信八(こにし のぶはち)1854年(嘉永7)―1938年(昭和13)
長岡藩医小西善硯の次男として越後国古志郡高山村(現・長岡市高島町)に生まれ、1876年(明治9)東京師範学校中学師範科に入学し、1877年(明治10)、東京高等師範学校教諭(付属幼稚園主任を兼務)、1878年(明治11)には文部省四等属に任ぜられて訓盲啞院掛事務となります。そして1879年(明治12)に東京盲啞学校教諭兼幹事となり、さらに1882年(明治15)の同校校長心得を経て、1885年(明治18)に39歳で同校校長となっています。そして、1902年(明治35)に東京盲啞学校が東京盲学校と東京聾啞学校に分離した際、後者の校長として1925年(大正14)まで務めました。
盲唖学校・聾唖学校校長、初期聾唖教育・盲教育の充実に努め、欧米歴訪で国家の教育を受ける「権利」・義務制の主張を明確化する。石川倉次と共に6点点字の開発。盲・唖分離論を唱えました。明治・大正という、障害者教育の黎明期に大きな足跡を残しました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
「点字教育と新潟 – 博物館学を読む – Yahoo!ブログ」
2.大森隆碩(おおもり りゅうせき)1846 年(弘化3)―1903 年(明治36)
「医学と英語の英才」
1846 年(弘化3)高田藩医の長男として誕生。15 歳からは江戸で眼科の勉強をし、1864 年(元治1)に高田で眼科医を開業します。そしてさらなる医学の上達を志し、英語を学ぶため大学南校(現・東京大学の前身の一つ)に入学します。ヘボン式ローマ字で知られる医師ヘボンにも師事し、ヘボンの和英辞典編さんを手伝うまでに英語が上達しました。
「訓盲談話会」の設立
再び高田へ戻った隆碩は自らも失明の危機を経験したことから、目の不自由な人たちの教育について考えるようになります。1886年(明治19)には医師や視覚障害者たちとともに「訓盲談話会」を設立し、幹事長に就任。翌年には早くも高田寺町の光樹寺(寺町2)で、目の不自由な子どもたちを集め、鍼灸・あんま、楽器などの授業を始めることになりました。この光樹寺の学校が、のちに高田盲学校へと発展していくのです。この間、隆碩は「医事会」「高田衛生会」などの医療団体の設立にも尽力しています。
「高田盲学校」
1891 年(明治24)、隆碩は再三の申請の末ようやく県から認可を受けて、私立高田訓矇(くんもう)学校を設立し、校長に就任します。日本で三番目の盲学校の誕生です。隆碩はその私財の多くを訓矇学校の運営費に充てていました。またこの頃、隆碩は中頸城郡立産婆養成所の設立にも貢献し、その所長も務めています。1903 年(明治36)、療養中だった東京で亡くなりました。享年57 歳
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
「日本3番目の盲学校を開校 大森隆碩」
「開学の精神」後世に
「高田盲学校の設立に尽力した眼科医・大森隆碩」
3.大森ミツ(高岡清次と結婚し、高岡光子)
大森隆碩の次女 東京盲唖学校訓導。1904年(明治37)国定教科書「地理書」に挿入する『内国地図』を亜鉛版に打ち出し発行(初の触地図)。翌 1905年(明治38)8月には『外国地図』を発行。1914年(大正3)には辞書『言海』の点字訳を成し遂げました。夫・高岡清次は東京帝大を卒業後に中途失明した法学徒であり、光子はその学問をも支えました。なお、1909(明治42)年2月国に対して「点字公認ニ関スル請願」が提出され、あと一歩で採択されるところまで進展しましたが、内閣法制局の「点字は文字にあらず」という判断によって葬り去られました。この請願に高岡清次も加わっています。
4.市川信夫 1933年(昭和8)-2014年(平成26)
新潟県上越市出身。高田瞽女の文化を保存・発信する会代表。児童文学者。新潟大学教育学部に学び、各地の小学校に勤めた後、盲学校・養護学校などで障害児教育に当たりました。高田瞽女研究の第一人者と言われた父、市川信次の指導で瞽女研究をはじめました。退職後は知的障害者通所作業所所長、上越市文化財審議委員などを歴任。坪田譲治氏に師事して学んだ児童文学の分野では、代表作に「雪と雲の歌」や映画化された『ふみ子の海』(理論社)があります。その映画のキャッチコピーは「ほんとうに大切なものは目に見えない」でした。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
「児童文学者・高田瞽女研究家、市川信夫さん死去 功績たたえ、急逝を悼む」
「瞽女文化」
「ふみ子の海」
5.高田訓矇学校は「日本最初の盲学校」
(点字毎日連載『歴史の手ざわり・もっと!第10回』より)
明治10年代、東西二校の他に、大阪や石川などで盲啞教育が試みられました。しかし、条件が熟していなかったため、いずれも挫折してしまいました。従って、1891年(明治24)創立の高田盲学校が「3番目の盲学校」と言い習わされてきました。現在(執筆・掲載時点)は、県立上越養護学校内に同新潟盲学校高田分校となっています。
高田盲学校の歴史は幾つかの際立った特色を持ちます。まず、2006年(平成18)まで、一度も「盲唖学校」に変容することなく、徹頭徹尾「盲学校」として存在し続けた点です。京都も東京も、「盲唖」校であった時期に、高田は視覚障害に特化した学校づくりを初心としました。地元には、聾唖生の受け入れを望む動きもありましたが、それをあえて退けました。この経緯をふまえると、高田は「3番目」でなく、「日本で最初の盲学校」と称えるのが相応しいとさえ言えます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
「点字毎日 2011年10月27日 歴史の手ざわり・もっと」 岸博実
これらの方々の足跡・業績をいっそう体系的に掘り起し、顕彰していきたいと念じます。高田盲学校の史料、市川信夫氏の仕事をどう継いでいくか、関係者のご尽力に期待しています。
PS:ささやかなお土産として、「高田盲学校30周年記念」(点字)を墨字に起こして持参いたしました。
略歴
1972年(昭和47年) 広島大学教育学部卒業
1974年(昭和49年)~ 京都府立盲学校教諭
2011年(平成23年)~ 点字毎日・点字ジャーナルに盲教育史連載
2012年(平成24年)~ 日本盲教育史研究会事務局長
2013年(平成25年)~ 滋賀大学教育学部非常勤講師
6月 盲人史国際セミナーinパリで招待講演を担当
2014年(平成26年)7月 第23回視覚リハビリテーション研究発表大会で教育講座を担当
後記
とにかく視覚障害者への教育の歴史に対する岸先生の真摯さ優しさを感じる講演でした。一つ一つは知っている積りでしたが、歴史の流れの中で語られた視覚障害者(児)の教育の話は新鮮でした。衝撃でした。最初に述べられた、琵琶法師・按摩師は、「見えない歴史や見えない体内」を記憶と手の力で操作した人たちという認識も新鮮でした。わが国には、古くから視覚障害者に対する施策や教育があったこと、明治を機に大きく制度改革が行われたこと、視覚障害者のために点字の開発が大きかったこと、盲・聾教育の義務化と分離に長い年月を要したこと(最近は逆に統合が進められている)。自己実現を求め続ける『主体』が形成・確立されてきた過程を知るにつれ、公助の範囲を縮小するかのような今日の流れに危惧を覚えます。
新潟の先達の働きも再認識しました。同時に、貴重な資料の保存も気になりました。あいにくの天候の中、京都から新潟(そして上越・高田)までお出で頂いたことに感謝します。
岸博実先生の、今後益々のご活躍を祈念致します。
我が国の視覚障害者のリハビリテーションの歴史
案内:第232回(15‐06月)済生会新潟第二病院眼科勉強会 吉野由美子
案内:第232回(15‐06月)済生会新潟第二病院眼科勉強会 吉野由美子
演題:「我が国の視覚障害者のリハビリテーションの歴史」
講師:吉野 由美子 (視覚障害リハビリテーション協会)
日時:平成27年06月03日(水)16:30 ~ 18:00
場所:済生会新潟第二病院 眼科外来
http://andonoburo.net/on/3598
抄録
リハビリテーションという言葉の定義は、元々がキリスト教における「波紋を解き、身分を回復する」という意味から派生して「再び相応しい状態に戻す」の意味から、人生の半ばで何らかの障害を負った方たちに対して、生活や社会活動において失われた機能を回復させるための様々なサービスと規定されていますが、私がここでお話しする視覚障害者に対するリハビリテーションは、幼い頃からの視覚障害者や中途視覚障害者等すべての方たちの生活を向上させるためにおこなわれている医療・福祉・教育に関わる広範囲なサービスについて取り上げて、我が国におけるその歴史的展開について言及したいと思います。
また、私の話す視覚障害リハビリテーションの歴史は、視覚障害(ロービジョン)と肢体障害という重複障害を持った当事者として67年生きてきたことと、約40年間視覚障害リハビリテーションを我が国に普及させようと努力してきた私自身の経験から「これが我が国の視覚障害リハビリテーションの発展の重要ポイント」だと思ったことをピックアップして述べさせていただきたいと思います。少し偏った視覚障害リハビリテーションの歴史になるかもしれませんが、今後の我が国の視覚障害者に対するサービスの未来を考える時の一つの問題提起として聞いていただければ幸いです。
プロフィール
1947年 東京生まれ 67歳
1968年 東京教育大学(現筑波大学)付属盲学校高等部普通科卒業
1974年 日本福祉大社会福祉学部卒業後、名古屋ライトハウスあけの星声の図書
館に中途視覚障害者の相談業務担当として就職(初めて中途視覚障害者と出会う)
1991年 日本女子大学大学院文学研究科社会福祉専攻終了(社会学修士)
東京都立大学人文学部社会福祉学科助手を経て1999年4月から2009年3月まで高知女子大学社会福祉学部講師→准教授 高知女子大学在任中、高知県で視覚障害リハビリテーションの普及活動を行う。
2009年4月より任意団体視覚障害リハビリテーション協会長(現在に至る)
ネット配信
今回の勉強会の一部は、「新潟大学工学部渡辺研究室」と「新潟市障がい者ITサポートセンター」のご協力によりネット配信致します。以下のURLにアクセスして下さい。
http://www.ustream.tv/channel/niigata-saiseikai
当日の視聴のみ可能です。当方では録画はしておりません。録画することは禁じておりませんが、個人的な使用のみにお願いします。
消防訓練のお知らせ
消防訓練をA8病棟にて実施します。
日時:5月29日(金)15時から16時までを予定
内容:「院内放送」
訓練に沿った院内放送が流れます。ご理解の上、ご協力をよろしくお願い致します。
なでしこCheers!5月号を掲載しました。
なでしこCheers!5月号を、広報誌・パンフレットページに掲載しました。
ぜひご覧ください。
クールビズ実施しています。
済生会新潟第二病院では、病院全体でクールビズ(ノーネクタイ・ノー上着など)を行っております。
ご理解・ご協力をお願いいたします。
期間:5月1日〜10月31日
障がいのある人もない人も一人ひとりが大切にされいかされる新潟市づくり条例検討会に参加して
案内:第231回(15‐05月)済生会新潟第二病院眼科勉強会 遁所直樹
演題:「(仮称)障がいのある人もない人も一人ひとりが大切にされいかされる新潟市づくり条例検討会に参加して」
講師:遁所 直樹(社会福祉法人 自立生活福祉会事務局長)
日時:平成27年05月13日(水)16:30 ~ 18:00
場所:済生会新潟第二病院 眼科外来
http://andonoburo.net/on/3555
抄録
障害者権利条約(Convention on the Rights of Persons with Disabilities)とは、あらゆる障害者(身体障害、知的障害及び精神障害等)の、尊厳と権利を保障するための人権条約です。
この条約は、21世紀では初の国際人権法に基づく人権条約であり、平成 18年12月13日に第61回国連総会において採択されました。日本国政府の署名は、平成 19年9月28日です。平成 25年12月4日、日本の参議院本会議は、障害者基本法や障害者差別解消法の成立に伴い、国内の法律が条約の求める水準に達したとして、条約の批准を承認しました。日本国の批准は平成 26年1月20日付けで国際連合事務局に承認されています。
現在、新潟市では、「障がいの有無に関わらず、誰もが暮らしやすく、市民一人ひとりが尊重される共生社会の実現」を目指し、本市独自の障がい者差別解消を図る「(仮称)障がいのある人もない人も一人ひとりが大切にされいかされる新潟市づくり条例」の制定に向け、検討を重ねているところです。
来年度新潟市議会に承認を受けたのちに条例として成立することになりますが、その内容について現在の状況をお話ししたいと思います。
プロフィール
新潟大学大学院博士課程1年時頚椎 4番5番骨折頚髄損傷
平成10年から介護老人保健施設ケアポートすなやま勤務
平成12年から NPO法人自立生活センター新潟勤務
平成23年から社会福祉法人自立生活福祉会事務局長
新潟市障がい者施策審議会委員
仮称)障がいのある人もない人も一人ひとりが大切にされいかされる新潟市づくり条例検討会委員
参考
遁所さんが勉強会でお話するのは、今回が4回目です。これまでの講演要旨を以下に記します。
第91回 2003年12月10日
「期待せずあきらめず」 遁所 直樹
新潟市障害者生活支援センター分室
http://andonoburo.net/on/3537
第121回 2006年4月12日
「なぜ生まれる無年金障害者」遁所 直樹
NPO法人自立生活センター新潟 副理事長兼 新潟学生無年金障害者の会 代表
http://andonoburo.net/on/3546
第188回 2011年10月12日
「NPO法人から社会福祉法人へ ~ 自立生活福祉会、今からここから」
遁所 直樹 社会福祉法人自立生活福祉会 事務局長
http://andonoburo.net/on/3551
ネット配信について
今回の勉強会の一部は、「新潟大学工学部渡辺研究室」と「新潟市障がい者ITサポートセンター」のご協力によりネット配信致します。以下のURLにアクセスして下さい。
http://www.ustream.tv/channel/niigata-saiseikai
当日の視聴のみ可能です。当方では録画はしておりません。録画することは禁じておりませんが、個人的な使用のみにお願いします。
泌尿器科の特色・取り組みページを更新しました
泌尿器科の特色・取り組みページに、
「初心者の初心者のための平岡・吉水式HoLEP」の抄録を追加しました。