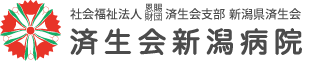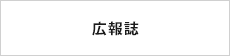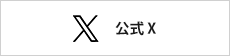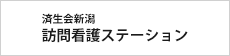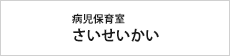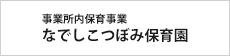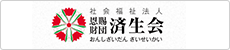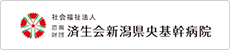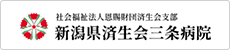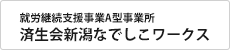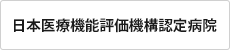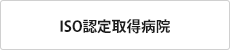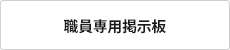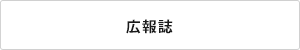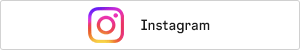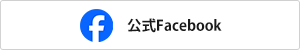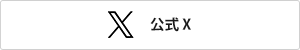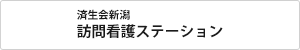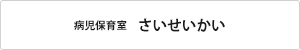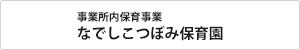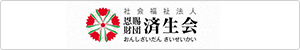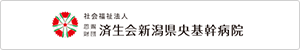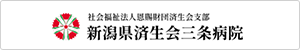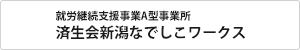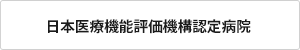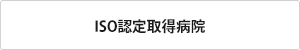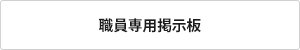報告:『済生会新潟第二病院眼科公開講座 治療とリハビリ』 高橋政代(理研)
眼の愛護デー(10月10日)に、8都府県から眼科医・内科医・神経内科医・リハビリ医・麻酔医やリハビリ関係者・教育者・当事者等々、約60名が参加し、済生会新潟第二病院10階会議室で公開講座「治療とリハビリ」を行いました。
今回、高橋政代先生(理化学研究所CDB)の講演要約を参加者の感想と共に紹介します。
特別講演2:「iPS細胞による眼疾患治療の現状と未来」
講師:高橋政代(理化学研究所CDB 網膜再生医療研究開発プロジェクト)
http://andonoburo.net/on/4133
講演要約
2013年8月に初めてのiPS細胞を用いた移植臨床研究が承認を得て、1例目の手術は2014年9月に施行された。2006年にマウスiPS細胞、2007年にヒトiPS細胞が発明されてから驚くほど短期間での臨床応用と言われる。しかし、今回の臨床研究の準備はすでに10年以上前からES細胞を用いて、網膜細胞治療という構想からいうと20年前からスタートしていた。基礎研究からヒトに応用するまでにはやはりそれだけの年月が必要である。研究を進めている期間に様々な否定的意見を聞いたが、網膜細胞治療の最終像を考えるとそれらは論理的に心動かされ方針を変更させるものではなかった。
我々のラボにフィールドワーク(!)に来て研究者という人種を研究している人類学者に言わせると、高橋は過去、現在、未来の順で考える思考と異なり、未来像から遡って現在を考えるという思考法だそうだ。再生医療ができることが自明のように語る私と他の人と話が合わないのがなぜかずっと不思議であったが、とんと合点がいったような気がする。
今回の臨床研究では自家iPS細胞由来網膜色素上皮(RPE)細胞シートを移植し手術後1年間で結果を判定する。移植する細胞シートは様々な品質検査や免疫不全マウスを用いて繰り返し行った造腫瘍性試験で安全性が確認された。現在手術後1年の判定期間が終了したが、主要評価項目の安全性については、拒絶反応、腫瘍化、手術による重篤な合併症などを認めず順調に経過している。世界ではiPS細胞を使った治療は主要ができるのではないか、自分の細胞を使う自家移植であっても培養の期間に変化がおきて拒絶反応がおこるのではないか、などの懸念を持つ研究者がほとんどであるが、1例ではあるが、それが杞憂であることを示した。絶対に失敗できないプロジェクトであったので、リスクは考え尽くしてあり、1例目は視力の経過や患者の反応まで含めて予想通りであった。2例目3例目も同様であると考える。
再生医療の問題の一つはその言葉からもたらされる過剰な期待である。再生医療(細胞移植治療)はまったく新しい治療であり最初は効果も小さい。治療の効果と安全性の進歩のシグモイド曲線は白内障手術などで眼科医は経験ずみである。再生医療も同様で、改良を重ねて徐々に効果的な治療となることが考えられるが、それらの正しい情報はなかなか一般に伝わりにくい。今回の臨床研究では網膜感度上昇などの効果判定は副次項目であるが、過剰な期待は治癒が唯一の問題解決法であるという思い込みから来ることが多い。特に網膜の場合は成功してもまだまだ視機能は低く停まることが考えられ、再生医療はリハビリテーション(ロービジョンケア)とセットで完成すると言える。再生医療は網膜以外でも同じでリハビリテーションとセットであること認知されてきている。今後は、臨床研究、先進医療、治験、治療、リハビリ、患者ケアが一体となったメディカルセンターが求められる。
我々は、神戸にそれらを包括したアイセンターを構築しようと計画している。アイセンターは先端医療センターの眼科専門病院、理研の研究部門、ロービジョンケアと社会実験のための公益社団法人NEXT VISIONの3者が協力して運営する。再生医療の高い認知度を利用して、視覚障害に対する一般社会の理解を高めることができることが可能かもしれない。そのために作ったNEXT VISIONでは、ロービジョンケアや視覚障害のイメージ変革と推進、デバイスの開発や社会実験を行う。日本で歴史も古く充実している全盲者に対するケアとは異なり、眼科医が日々接するのにケアが抜け落ちている軽度の視覚障害、就労を続けられるのに諦めてしまう人々を主に対象にして、企業、産業医、眼科医、しいては支援施設、当事者においても視覚障害に対するイメージを変革することが必要であり、可能かもしれないと考えている。
略歴
1986 京都大学医学部卒業
1986-1987 京都大学医学部附属病院眼科 研修医
1987-1988 関西電力病院眼科 研修医
1992 京都大学大学院医学研究科博士課程(視覚病態学)修了
1992-1994 京都大学医学部附属病院眼科 助手
1995-1996 アメリカ・サンディエゴ ソーク研究所研究員
1997-2001 京都大学医学部附属病院眼科 助手
2001-2006 京都大学医学部附属病院探索医療センター開発部 助教授
2006-2012 理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター
網膜再生医療研究チーム チームリーダー兼任(2006年10月より専任)
2012-2014 理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター
網膜再生医療研究開発プロジェクト プロジェクトリーダー(*)
2014-現在 理化学研究所 多細胞システム形成研究センター
網膜再生医療研究開発プロジェクト プロジェクトリーダー(*)
(*)組織改正により変更
参加者から
●iPS細胞を移植する再生医療が、世界で初めてわが国で臨床治験された。最初の臨床治験が行われてから1年の臨床経過を示してもらった。今後は、F1カー(個別のiPS細胞)ばかりでなく、カローラ(iPS細胞バンク)も用意するという。治療選択肢が増えるのはいい進歩。診療・研究・リハビリを兼ねた「アイセンター」構想が、より具体化している。企業の方も参加し戦略として進めているという。もはや医学医療を飛び越えたスケールのでかいお話でした。現在の閉塞した医療の現実を考える時、新しい医療の形を示す「アイセンター」構想の実現を願います。(新潟市/眼科医/男性)
●いつ拝聴しても凄いとしか言い様がありません。本当の意味での【アイセンター】が実現すれば素晴らしいと考えています。其の為には、行政を逆手に取っておられると感じました。講演後に某名誉教授曰く、「色々な女傑を見てきたが、彼女が一番だね」。(新潟市/医療機器販売/男性)
●iPSの現状と将来への展望がわかり興味深かったです。(新潟市/眼科医/男性)
●とても興味深いものでした。 たまたま、前はやぶさプロジェクトマネージャーの川口という人の話をみかけたのですが、彼はプロジェクトで大切なのは、100点を目指さないこと、60点を100%の確率で実現することと語っています。また、心配していたことがおきてしまうのは、3流、予想もしていなかったことが起きてしまうのは二流、一流とは、何もおきないことといいます。高橋先生が治療に使われたもののサイズがそのままだったようにお聞きしたことが、この何もおきないことなのかと思いました。川口氏は、研究ではなくプロジェクトをやる、プロジェクトを進める上では、技術よりむしろ根性が大きな要素と言ってます。全くの雑談ですみません。大きな仕事をやられる方は、有能なプロデューサーなんだなあとたまたま同時期に感銘をうけたものですから。川口氏は、(安藤先生と同じ)青森県出身なのですね。(新潟市/眼科医/女性)
●視野の広さ、考えを行動に移すその速さバイタリティーに感服し、私の残された時間の中で、1症例を思い出して、なんとか助けてあげたい事をご相談し先端医療センター眼科の受診方法を教えていただきました。一人でも失明から救いたい想いの、今の私に有り難い貴重な時間でした。(新潟県/眼科医/女性)
●iPS細胞による治療法の前途について、大変分かりやすいものでした。講演の初めに、理研の研修生の一人の方が、チンパンジーの行動の研究をするようにスタッフの行動を観察し、それによると高橋先生が将来の理想形から物事を考える珍しいタイプであると言われた。しかしこれは企業的な発想では当たり前のこと、とおっしゃったことが印象深いものでした。最も刺激的だったことは、高橋先生のプロジェクトが二重にも三重にも多様な道を用意しておられることです。すべてが同じ方向を向いているが、多様なニーズに合わせて多様な選択肢を作っておられることは万全の準備が見通せていてリーダーとして素晴らしい発想と思いました。また、シートを入れる治療法と浮遊性の治療と、どんどん新しい治療が進んでいることを教えていただきました。ロービジョンのリハビリや就労についての展望も、患者さんの未来にとってより積極的な社会参加を促すだけでなく、社会にとっても人的財産の貴重な損失を免れることになり、大きな前進と思います。(神奈川県/音楽家/女性)
●この公開講座は設定がよく、学ぶところ多い。高橋政代氏の科学者としての計画性、実行性、将来性、すべてすばらしく、りっぱなもの。貴重な存在なるも、一般に期待されているのは病気をなおすことだけで、リハビリに深く思いを致していることが全然社会にはわかっていない。卑近なはなしですが、10月10日は目の愛護デーなのに、体育の日にすりかえられて、だれも目の愛護デーなど知らないのが現実。なさけないことだね。 Eye cennter構想が広く実現するには困難がおおいことと痛感。(新潟市/眼科医/男性)
●どんどん進化しているんですね。研究ばかりやっていらっしゃるのかと思ったら、ちゃんと患者さんもみて、患者さんの困っていることをちゃんと把握して、対策を考えていらっしゃって、すごいと思いました。(新潟市/神経内科医/女性)
●iPS細胞での治療もいろんな事を考えて慎重に進んでいることが分かり、頼もしくも思えたのですが、歯がゆくも思いました。そして、リハビリ、支援を考えて、トータルに医療をなしてゆく姿勢に、敬服です。(新潟市/内科医/男性)
●患者さんを中心とした眼科医療のありかたをトータルで考えられて研究されているというお話には感銘を受けました。(新潟県/眼科医/男性)
●講演後半に 公益財団法人 NEXT VISION のお話をされました。法人の存在は初耳だったので、さっそくネットで調べました。アイセンター構想は新鮮で、ワンストップ型の理想形ですが、事業化できればすばらしいと感じました。(新潟市/病院職員/男性)
●今や時の人である先生のご講演も最先端の医療を分かりやすく、お話いただきました。理想の目標をあらかじめ設定して、そこに様々な紆余曲折アプローチを繰り返し、最終的にゴールに到着する事に尊敬致しました。(新潟市/薬品メーカー社員/男性)
●まさに今最先端の再生医療の話と、さまざまな活動、またその裏側の研究の現状や高橋先生の実際の思いなど、テレビやマスコミなどでは伝わらない内容を直に拝聴できました。 特に、アイセンターの話は、眼科医、研究者というご側面もありながら、ロービジョンケア全体を大局的に見た長期ビジョンをお持ちで、それを展開してく熱い思いが伝わってくる非常に感慨深いご講演でした。(新潟市/薬品メーカー社員/男性)
●自分も眼科メーカーの社員ということもあり、高橋先生の講演がとても印象に残りました。ES細胞、iPS細胞の違いという初歩的な内容から、なぜRPEを再生させ、1件目の手術としたかなど学ばせていただきました。また、普段は、どうしても臨床データ、基礎データに触れることが多い環境なので、基礎~ビジネスまでの流れをご紹介いただいたことに改めて製品の上市の難しさを実感できました。再生医療の場合は、さらに遺伝子学関係者、倫理関係者等が加わり、その難しさは想像できませんでした。大きな脚光を浴び、順風満帆な分野という印象しかなかったので、驚きました。(東京/医療機器メーカー/男性)
●私はiPS細胞の臨床応用が2例目でなぜ中止になったのか、どういう部分で疑問を持たれたのか、そこが知りたかったし一番興味があったところです。テクニカルなことよりも行政との関係であるようなお話でしたが、私の事前勉強が足りないせいで、あまりよく理解できませんでした。それでもiPS細胞由来のRPE細胞移植はがん化も含めて、やはり臨床応用できる安全レベルであること、さらに企業が参入して移植用の細胞を製造するコストまでを含めた実用化が進行していることなど、最先端で指揮している先生から直接お話を聴くことができて感謝しています。私は高橋先生のお話を聴くのは二回目ですが、前回と高橋先生の印象はずいぶん違いました。前回は世界を相手の学者といった感じで近寄りがたい雰囲気でしたが、今回は女性らしいやわらかさを感じました。それは、神戸医療産業都市アイセンター構想という、スマートサイトを集約するような、とてつもなく大きくて、やさしくて、あたたかいシステムのお話を聴いたせいかも知れません。ぜひ実現させてほしいし、そのための協力なら惜しみません。まぁ、私が協力できることなど無いでしょうが(笑)(新潟県/自営業/男性)