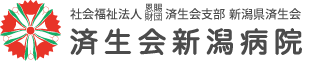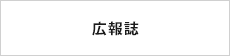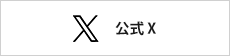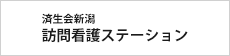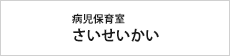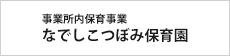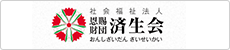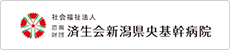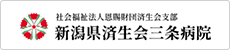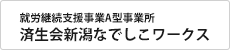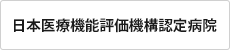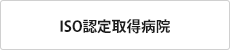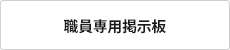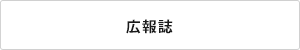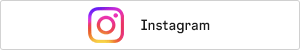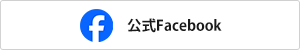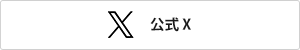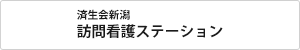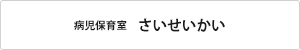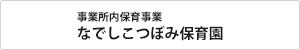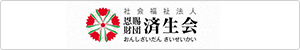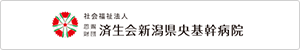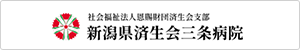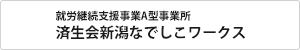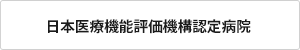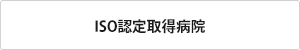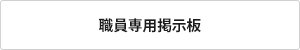詳しくは採用情報ページをご覧ください。
All posts by c15eehzg
調理師(正)と看護師(準)を募集しています
詳しくは採用情報ページをご覧ください。
済生会が目指すソーシャル・インクルージョンの実現
報告:第258(17-08)済生会新潟第二病院眼科勉強会 小西明
日時:平成29年08月09日(水)16:30 ~ 18:00
場所:済生会新潟第二病院眼科外来
演題:済生会が目指すソーシャル・インクルージョンの実現
~人々の「つながり」から学んだこと~
講師:小西 明(済生会新潟第二病院医療福祉相談室)
http://andonoburo.net/on/6116
講演要約
1 はじめに
近年、国家財政の悪化を理由に医療費の患者負担の増額、介護や社会保険料の引き上げなどが行われ、国の医療や介護、福祉経費は抑制され厳しさを増している。一方で障害者だけでなく低所得世帯の子どもや高齢者、引きこもりなどによるニートやホームレスなど、さまざまな理由による生活困窮者がマスコミで取り上げられている。総じて行政は、法制度の枠組みの中でのサービス給付は得意だが、非定型なニーズに対して実効性のある支援は苦手と言われている。社会には「公共の手」からこぼれ落ちる人たちがいて、昨今は、そういう人たちが増えている。
2 ソーシャル・インクルージョン(social inclusion)
1950年代、デンマークのバンク・ミケルセンは第二次世界大戦後に、知的障害者を持つ親の会の運動に関わっていた。当時の知的障害者は、隔離された大規模施設に収容され、非人間的な扱いを受けていた。そのような状況下で、親が「親の会」を結成して組織的に反対運動を展開した。ミケルセンは「どのような障害があっても、一般の市民と同等の生活・権利が保障されなければならない。障害者を排除するのではなく、障害をもっていても健常者と均等に当たり前に生活できるような社会こそがノーマルな社会である。」とした、ノーマライゼーション(normalization)の理念を提唱した。
ソーシャル・インクルージョンは、ノーマライゼーションを発展的に捉え、障害者だけでなく「全ての人々を孤独や孤立、排除や摩擦から援護し、健康で文化的な生活の実現につなげるよう、社会の構成員として包み支え合う」という理念である。炭谷茂済生会理事長は、ソーシャル・インクルージョンを済生会の目指す地域サービスの基本と提言している。
3 済生会のあゆみ
済生会は明治44(1911)年2月、明治天皇が「恵まれない人々のために施薬救療による済生の道を広めるように」との済生勅語に添えて、150万円を下賜されたことが始まりである。時の総理大臣桂太郎は、この御下賜金を基金として全国の官民から寄付金を募り、同年5月30日恩賜財団済生会が設立された。以来、100年以上にわたり創立の精神を引き継ぎ、保健・医療・福祉の充実・発展に必要な諸事業に取り組んでいる。医療によって生活困窮者を救済しようと明治44(1911)年に設立した。100年以上にわたる活動をふまえ、現在では、日本最大の社会福祉法人として全職員約59,000人が40都道府県で医療・保健・福祉活動を展開している。
4 済生会の事業
社会福祉法人済生会は、定款の第1条に「本会は 済生会創立の趣旨を承けて済生の実を挙げ、社会福祉の増進をはかることを目的として全国にわたり医療機関及びその他の社会福祉施設等を設置して次の社会福祉事業等を行う。」とある。全国に病院・診療所などの医療機関を中心に、児童福祉施設や障害者福祉施設、高齢者福祉施設や看護専門学校の事業を運営している。
5 済生会新潟第二病院の特長
当院は生活保護法患者の診療及び生計困難者のための無料又は低額診療等を実施している。減免相談対象者は、生活保護適用外の生計困難者(年金生活、不安定就労など)やDV被害者、人身取引被害者等の社会的援護を要する方々などである。加えて、昨今の社会経済情勢の中で、医療・福祉サービスにアクセスできない人々が増加しつつあることから、済生会創立の理念に立ち返り、福祉の増進を図るため済生会生活困窮者支援事業「なでしこプラン」を積極的に展開している。
事業は、①DV被害者支援 ②更生保護施設「新潟川岸寮」の医療支援・社会貢献活動・研修会 ③外国籍住民のための医療相談会 ④東日本大震災避難者支援である。
また当院眼科では、地域貢献活動として、どなたでも参加できる眼科勉強会・新潟ロービジョン研究会・市民公開講座が開催されている。地域連携福祉センターでは、市民向けおきがる座談会、事業所向け出前講座などを開催している。
6 展望
(1)障害者をはじめ、全ての人々にやさしい病院
障害者をはじめ、子どもや高齢者など社会的弱者に「医療関係事業者向けガイドライン」に基づいた合理的配慮の視点による、より「やさしい病院」を目指してほしい。
(2)医療と教育の連携
県内にこども病院、小児療育センター、児童発達支援センターの開設が望まれる。また、 特別支援学校生徒の当院院内実習を通して、障害者の自立や社会参加への支援、職員への理解啓発を図っている現状を報告した。
(3)ソーシャル・ファームの開設
通常の労働市場では就労の機会を得ることの困難な者に対して.通常のビジネス手法を基本にして仕事の場を創出する。主たる対象は障害者であるが、高齢者、母子家庭の母親ニート・引きこもりの若者、刑余者、ホームレスなどである。当院がリーダーシップを発揮し、ソーシャル・ファームが早期に開設されることを望む。
(4)知的障害者の福祉型大学
インクルーシブ教育システム推進の観点から、将来は知的障害者が高等教育機関で学ぶことができる課程の創設が望まれる。当面は高等部卒業後の進路選択肢の拡大を目指し、現状の福祉制度を活用した類似施設の開設が考えられる。
【略 歴】
1977年 新潟県立新潟盲学校教諭
1992年 新潟県立新潟養護学校はまぐみ分校教諭
1995年 新潟県立高田盲学校教頭
1997年 新潟県立教育センター教育相談・特殊教育課長
2002年 新潟県立高田盲学校校長
2006年 新潟県立新潟盲学校校長
2015年 済生会新潟第二病院医療福祉相談室勤務
=============================
【後 記】
今回は、小西明先生にお話して頂きました。小西先生は、長い間新潟県の教育畑に在籍し、主に視覚障害児の教育に関わってこられました。高田盲学校・新潟盲学校の校長を歴任され、退職後当院にお呼び致しました。
当院では、医療福祉相談室に勤務され多くの方面で活躍されています。一口に医療と教育の連携と言いますが、こうした人的交流がひとつの突破口になるのではないかと思います。
医療の現場での常識は、必ずしも教育の現場での常識ではありません。その逆も真なりです。小西先生の院内での発言は私たちに大きな影響力を持ち始めています。
今後ますますの小西先生のご活躍を祈念しております。
視覚障害者とスマホ・タブレット 2017
報告:第256(17-06)済生会新潟第二病院眼科勉強会 渡辺哲也
演題:「視覚障害者とスマホ・タブレット 2017」
講師: 渡辺哲也(新潟大学准教授:工学部 人間支援感性科学プログラム)
日時:平成29年06月14日(水)16:30 ~ 18:00
会場:済生会新潟第二病院 眼科外来
http://andonoburo.net/on/5967
視覚障害は情報障害である。今や携帯電話・スマートホンは、全盲を含めた視覚障害者にも生活必需品である。今回の講演は、視覚障害者におけるデジタルデバイス(スマートホン・タブレット端末機器)の使用状況についてのレポートであった。大いに関心を呼んだ。渡辺先生は、2013年にも同様な調査をしており、今回は2017年度版で前回との比較も示して下さった。わが国でこのような報告は他になく、貴重な報告であった。
講演要約
1. はじめに
厚生労働科研費を得て、視覚障害者のICT機器利用状況調査を実施した。今回の調査の主たる関心事は、スマートフォン・タブレットの利用率は上がったか、視覚障害者用のアプリはどのくらい使われているか、スマートフォン・タブレットにおける文字入力方法はどのようなものか、などである。
2. 調査の実施と回答状況
調査の実施は、中途視覚障害者の雇用継続を支援するNPO法人タートルに委託した。タートルは、視覚障害者が主に参加する約50のメーリングリストで回答者を募集した。調査期間は2017年2月20日からの1ヶ月である。
有効回答者は305人(男性192人、女性113人)、全員メールで回答をしており、情報機器を使い慣れている人たちである。障害等級は1級の人が最も多く208人(68.2%)、2級のヒトが69人(22.6%)だった。視覚的な文字の読み書きができるかどうかという質問に「できる」と答えた人をロービジョン、「できない」と答えた人を全盲とすると、ロービジョンの回答者が90人(全回答者の29.5%)、全盲の回答者が215人(同70.5%)だった。
3. ICT機器の利用率
携帯電話(いわゆるガラケー)の利用率は全盲の人で60.9%、ロービジョンの人で54.4%だった。スマートフォンの利用率は全盲の人で52.1%、ロービジョンの人で55.6%だった。タブレットの利用率は全盲の人で14.4%、ロービジョンの人で38.9%だった。
2013年に同様な調査をしたときの結果と比べると、全盲の人、ロービジョンの人ともに、スマートフォンの利用率が倍増した。タブレットの利用率はロービジョンの人では約2倍まで伸びたが、全盲の人では伸び率は1.5倍程度であった。他方で携帯電話の利用率は、2013年のとき全盲の人で85.8%、ロービジョンの人で73.7%だったのに比べると20%程度低下した。
年齢別にスマートフォンと携帯電話の利用率を見ると、全盲の人、ロービジョンの人ともに、年代が下がるほどスマートフォンの利用率が高く、携帯電話の利用率が低い傾向が見られた。
スマートフォンやタブレットを使い始めた理由としては、様々なアプリが使えて便利と、読み上げ機能が標準で付いていることが上位の回答となった。
逆にこれらの機器を使わない理由としては、現状の機器で十分と、タッチ操作ができない、難しそうという回答が多かった。
4. 機種
スマートフォン利用者157人(全盲の人107人、ロービジョンの人50人)に利用している機種を尋ねた。全盲の人、ロービジョンの人とも最も利用者が多かった機種はiPhoneで、全盲者の91.1%、ロービジョン者の80.0%が利用していた。Android端末の利用者数は全盲者で7人(16.3%)、ロービジョン者で9人(18.0%)と少なかった。全盲のらくらくスマートフォン利用者の数は4人(3.6%)に留まった。ロービジョン者でらくらくスマートフォンを利用する人はいなかった。2017年3月時点で、日本におけるiPhone利用率が45%であることと比較すると、視覚障害者のiPhone利用率は非常に高い。
5. アプリ
スマートフォンで利用しているアプリを、全盲の人とロービジョンの人の回答を足し併せて多いものから並べると、通話、メール、時計、アドレス帳、電卓、歩数計、ブラウザ、スケジュール、写真を撮る、という順序になった。スマートフォンで使えるようになった便利な機能として、画像認識、光検出、GPS/地図/ナビゲーションなどがあるが, GPS/地図/ナビゲーションの利用者は全盲の人で20人足らずであり、利用者が多いとは言えなかった。
6. 文字入力
スマートフォンにおける文字入力方法を詳細に尋ねた。文字入力手段としてソフトウェアキーボードの利用者数が、全盲の人とロービジョンの人の両方で最も多かった。全盲の人では、音声入力とハードウェアキーボードの利用者も多かった。
ソフトウェアキーボードの種類としては日本語テンキー、ローマ字キーボード、50音キーボードがある。全盲の人ではローマ字キーボードと日本語テンキーの利用者が多く、それぞれの利用率は61.1%と55.8%であった。ロービジョンの人では日本語テンキーの利用者が最も多く、利用率は76.1%、ローマ字キーボードの利用率は大きく下がり39.1%だった。
音声読み上げ(iPhoneではVoiceOver)をオンにすると、日本語テンキーにおける文字の選択・確定方法が変わり、ダブルタップ&フリック、ダブルタップ、スプリットタップなどのジェスチャが利用できるようになる。このうち、利用者が多かったのはスプリットタップとダブルタップであった。
7. 今後の仕事
スマートフォン・タブレットの利用状況の詳細のほかに、携帯電話・パソコンの利用状況についても、今後データを整理し、公表していく。
略歴
1993年 北海道大学大学院工学研究科生体工学専攻修了
1994年から2001年 日本障害者雇用促進協会 障害者職業総合センター(Windows用スクリーンリーダ95Readerの開発ほかに従事)
2001年から2009年 独立行政法人 国立特別支援教育総合研究所(漢字の詳細読み「田町読み」の開発ほかに従事)
2001年から現在 国立大学法人 新潟大学工学部(触地図作成システムtmacsの開発ほかに従事)
併任で、筑波技術大学 非常勤講師、国立身体障害者リハビリテーションセンター学院非常勤講師、NHK放送技術研究所 客員研究員
渡辺哲也先生の講演歴
渡辺先生には、これまで本勉強会で2度、第22回視覚障害リハビリテーション研究発表大会で一度講演して頂いています。
以下に、講演要約を記します。
1)第167回(10‐01月) 済生会新潟第二病院 眼科勉強会
演題:「視覚障害者と漢字」
講師:渡辺 哲也(新潟大学 工学部 福祉人間工学科)
日時:平成22年1月13日(水)16:30~18:00
場所:済生会新潟第二病院 眼科外来
http://andonoburo.net/on/5940
2)第205回(13‐03月)済生会新潟第二病院 眼科勉強会
演題:「視覚障害者とスマートフォン」
講師:渡辺 哲也 (新潟大学 工学部 福祉人間工学科)
日時:平成25年3月13日(水)16:30 ~ 18:00
場所:済生会新潟第二病院 眼科外来
http://andonoburo.net/on/5947
3)第22回視覚障害リハビリテーション研究発表大会 講演要旨
特別企画『視覚障害者とスマートフォン』
講師:渡辺 哲也 (新潟大学工学部 福祉人間工学科)
日時:平成25年6月22日(土)
場所:チサンホテル&カンファレンスセンター新潟 越後の間
http://andonoburo.net/on/2218
参考資料
・新潟大学 工学部 福祉人間工学科渡辺研究室新潟大学 ホームページ
http://vips.eng.niigata-u.ac.jp/
・視覚障害者のパソコン・インターネット・携帯電話利用状況調査2007
http://vips.eng.niigata-u.ac.jp/…/Survey2…/Survey2007Jp.html
・視覚障害者の携帯電話・スマートフォン・タブレット・パソコン利用状況調査2013
http://dspace.lib.niigata-u.ac.jp/dspace/handle/10191/27807
後記
視覚障害は情報障害である。携帯電話・スマートホンは、全盲を含めた視覚障害者にも今や生活必需品である。今回の講演は、視覚障害者におけるデジタルデバイス(スマートホン・タブレット端末機器)の使用状況についてであった。大いに関心を呼んだ。渡辺先生は、2013年にも同様な調査をしており、今回は2017年度版で前回との比較も示して下さった。わが国でこのような報告は他になく、貴重な報告であった。
・視覚障害者(全盲の人、ロービジョンの人ともに)は、スマートフォンの利用率が2013年と比較して倍増した。一方で携帯電話の利用率は低下した。
・視覚障害者のスマートホン利用率は、地域に指導者がいるかどうかに大いに左右されるというコメントにも説得力を感じた。
・画像認識やGPSが活用されているかと思いきや、実際はメール・ブラウザ・歩数計等の方が利用率が高かった。
工学の成果を視覚障害者の情報に役立てようとしている渡辺研究室の研究を応援したい。そして目の不自由な方にとって便利で使いやすい情報機器がもっと発展することを願う。
地域包括ケアシステムってなに?
報告:第255回(17-05)済生会新潟第二病院眼科勉強会 斎川克之
演題:地域包括ケアシステムってなに?−新潟市における医療と介護の連携から−
講師:斎川 克之(済生会新潟第二病院 地域連携福祉センター副センター長 新潟市医師会在宅医療推進室室長)
日時:平成29年05月10日(水)16:30 ~ 18:00
会場:済生会新潟第二病院 眼科外来
http://andonoburo.net/on/5907
講演要約
■新潟市の概況
政令指定都市新潟市の概況は、以下のとおりです。人口80万、65歳以上の高齢者27.5%、75歳以上の後期高齢者13.6% 地域包括支援センター27カ所、要介護者数40,000人。急速に高齢化が加速している状況であり、2025年には、人口約76万人、65歳以上の高齢者30.3%、75歳以上の後期高齢者17.2%と試算されています。
■医療機関について
地域包括ケアシステムにおける医療の役割は極めて重要です。地域住民にとって最も身近で日々の健康相談含めたプライマリケアを担当してくださるのがクリニック・診療所です。初期診断と治療、そして場合によっては適切な病院への紹介など豊富な経験で地域の住民のかかりつけ医として機能を発揮します。また、関係機関にとっても地域住民にとっても圧倒的な信頼感と安心をあたえることのできる存在、それが病院です。病院にもいろいろな種別が存在します。大きくは4種類あり、高度急性期、急性期、回復期、慢性期です。それぞれの病院が機能と役割を果たしています。
■当院の概況
当院は、新潟市西部にある425床の地域医療支援病院です。当院がある新潟市内は、高度急性期や専門性の高い医療を担う医療機関が集中している地区です。その中にあり、当院の強みはまさに地域からの信頼の指標である「連携」です。医療連携を柱としながらも、近年は地域の多職種連携を含む地域連携に対する取り組みを積極的に行ってきました。その最前線で機能を発揮する部署が、地域医療連携室・医療福祉相談室・がん相談支援室・訪問看護ステーションの4部署から成る地域連携福祉センターです。
■医療福祉相談について
地域の方々にとって、最も知っていたきたい病院の窓口、それが医療福祉相談室、そして医療ソーシャルワーカーです。医療ソーシャルワーカーは、患者さんの病気の回復を妨げている色々な問題・悩みについて、本人(ご家族)と共に、主体的に解決していけるように相談に応じています。特に近年の急速な超高齢社会においては、退院支援の相談が最も多く、在宅での療養生活を見据えた丁寧な援助を行っています。
■地域の連携が強まるように
他の医療機関から、いかにスムーズに紹介患者を受け、またその後に地域に帰すか。そこには地域からの強い信頼関係を基盤とした連携の仕組みがあればこそであり、院内だけの取り組みだけでは不十分です。自院だけでなく「地域力」をいかに高めることができるか、地域の全体最適を考える必要があります。地域の各医療機関が持つ医療資源やマンパワーを合わせて、最大限に個々のパフォーマンスを発揮できるようにするための「接着剤」が地域医療連携室の役割だと考えます。新潟市では、市内8区に在宅における多職種が連携を深める会である「在宅医療ネットワーク」が20団体あり、各職種の相互理解、課題解決へのアプローチなどそれぞれの取り組みを積極的に行っています。当院は、西区を対象に「にいがた西区地域連携ネットワーク」の事務局を担い、会の企画運営などを行っています。
一方、介護保険法の地域支援事業には在宅医療・介護連携推進が大きく謳われております。そしてその推進の指標として(ア)から(ク)の項目を平成29年度中に実施すべきとされています。その中の1項目に「多職種連携の構築支援、関係機関からの相談窓口」があります。これを新潟市は、先に述べた在宅医療ネットワークの事務局を担ってきた病院の連携室に業務を委託する形をとり、名称を「新潟市在宅医療・介護連携ステーション」(以下連携ステーション)としました。またその連携ステーション11か所を束ねる役割として「新潟市在宅医療・介護連携センター」を新潟市医師会に委託しました。いわゆる在宅医療介護連携のノウハウを持ち合わせた病院の連携室に、この事業の最前線を委ねた結果となりました。地域住民の相談窓口である地域包括支援センターと連携ステーションの両輪が機能を発揮しているところが新潟市の大きな特徴です。
■地域包括ケアシステムとは
地域包括ケアシステム構築の取り組みにおいて、近年、医療介護分野では目まぐるしく制度の変革が行われてきました。現在、全国の各市町村は主体的に、この地域包括ケアシステムの構築を進めています。これまで述べてきたように、新潟市においては、病院や診療所などの医療機関と介護・福祉の事業所などとの協力体制を強めてまいりました。今一度、地域包括ケアシステムとは何か。正直に言って「これ」と指を指せるものはありません。言葉で表現するならば、「地域のみなさんが、健康な時も、病気になった時も、どんな時も、今まで住み慣れた地域で安心して暮らすことのできるまちづくり・地域づくり」を根底とし、市区町村が中心となり、「住まい」を中心に「医療」「介護」「生活支援・介護予防」を包括的に体制整備していくこと。その実現のためには、医療と介護、そして福祉の途切れのない連携体制はもちろんのこと、ヘルスケアに関連するさまざなまな領域の方々、そしてもっとも主役となる地域の住民の方々との広い連携、そして参加できる場が最も重要となります。
略歴
斎川 克之(さいかわ かつゆき)
・社会福祉法人恩賜財団済生会 済生会新潟第二病院 地域連携福祉センター 副センター長
・一般社団法人 新潟市医師会 在宅医療推進室 室長
職種:社会福祉士、医療ソーシャルワーカー、医療福祉連携士
平成 7年/新潟県厚生連・在宅介護支援センター栃尾郷病院SWとして就職
平成 9年/済生会新潟第二病院に医療社会事業課MSWとして就職
平成22年/地域医療連携室 室長
平成27年/地域連携福祉センター 副センター長
平成27年/新潟市医師会在宅医療推進室長 併任
後記
斎川氏は当院ばかりでなく全国でも活躍している医療福祉支援の専門家。流石に非常にわかりやすく、しかも丁寧なお話でした。参加者の関心も高く、盛り上がった勉強会になりました。
講演後のフリートークでは、「包括さん」には大変お世話になったなどの好意的な発言もありましたが、容赦のない発言・質問も炸裂。・「自分ファースト」の時代に共生社会を作ろうというのは、「絵に描いた餅」ではないか? ・医療介護連携の区割りが、病院ベースだ。町内会や小学校校区ベースがしっくりする。・学生からは、学生実習で南魚沼に行ってきたが、4世代家族の奥さんは生き生きしていた。新潟との違いを感じたとのコメントもありました。
なんといっても印象的だったのは、斎川さんの非常に真摯な姿勢でした。ICTが流行っている世の中ですが、こうした人と人の触れ合いが物事を進めていくのだと、斎川さんを見て学びました。
議論百出で終わりそうにない勉強会でしたが、こんなコメントで締めくくりました。「自分の健康や親の介護を人任せではなく、先ずは自分で考え、こういう包括システムを学ぼうということが大事ではないか。かつては「長男の嫁」が親の介護を担ってきた。しかし世界にも稀な長寿国となると、それも難しくなってきた。今、国は大きく体制を変えようとしているが、その実態は地方自治体に任されている。そんな状況下で、なんとか皆が上手く生きていこうという社会を作るために、多くの困難に立ち向かっている斎川さん達の活動を、私たちが支援したい。」
研究情報の公開について(オプトアウト)
当院は下記の研究を実施しています。この研究の対象者に該当する可能性のある方で、診療情報等を研究目的に利用または提供することを希望されない場合は、下記の問い合わせ先にお問い合わせ下さい。
認定看護師による出前研修
当院は、地域医療支援病院として、質の高い医療の提供とあたたかく心ある地域医療連携推進を目指しています。その中で、地域の医療従事者を対象に、我々が保有する多分野の専門的知識を活用して、各施設のニーズにあった学習内容と機会を提供し、地域医療の発展に貢献していきたいと考え、認定看護師出前研修を企画しました。
| 研修名 | 認定看護師による出前研修 |
|---|---|
| 到達目標 | 地域の医療機関に勤務する看護・介護職員が、各施設のニーズに合った講義を受講することで、現場で活かせる知識を習得することができます。 |
| 対象者 | 当院と連携している新潟市西区医療機関で働く医療従事者としています。 |
| 研修形態 | 研修依頼を受けた分野の認定看護師が、依頼元に出張して研修を行います。 |
| 研修内容 | 各分野で別途企画します。 |
| 評価方法 | 1.研修内容については、「新たな知識を得た」「明日から実践に活かせる」等について研修後にアンケート調査を行います。アンケート結果は、当院で集計してお返ししますので、研修の評価としてご活用ください。 2.企画の評価については、研修担当者へ「申し込みの理由」「満足度」等についてアンケート調査を行います。 |
| 実施時間・期間 | 2017年9月~2018年3月の月~金曜日(当院休診日を除く)です。 |
| 研修場所 | 依頼元の指定場所になります。 |
| 経費 | 研修担当者間の通信費用、研修資料のコピー代は、ご負担していただきますが、交通費を含む講師謝礼等は不要です |
| その他 | 6月|案内文等の作成 7月|案内文を連携施設に発送 11月|本企画の中間評価 3月|本企画の最終評価 |
管理栄養士(正)看護補助者(準)を募集しています
詳しくは採用情報ページをご覧ください。
当院会議室等施設利用(予約)方法の変更について
現在、外部の方も当院会議室等の利用(予約)ができる状況となっておりましたが、防犯の観点から利用について見直しました。このことから、利用(予約)方法を変更いたしますので、ご理解・ご協力をよろしくお願い致します。
平成30年度初期臨床研修医採用ページを更新しました
平成30年度初期臨床研修医採用試験を行います!
出願締切は 平成29年8月10日(木)当日消印有効です。ご応募お待ちしております。
詳しくはこちらをご覧ください。
※当院は臨床研修マッチングプログラムに参加し募集を行います。