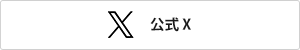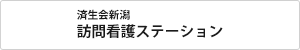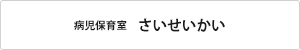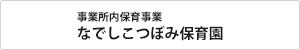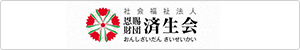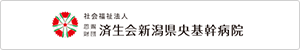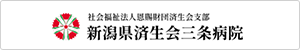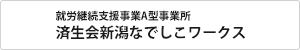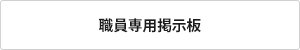物語としての病い
報告:第252回(17‐02月)済生会新潟第二病院眼科勉強会 宮坂道夫
演題:「物語としての病い」
講師:宮坂道夫(新潟大学医学部教授)
日時:平成29年02月08日(水)16:30 ~ 18:00
場所:済生会新潟第二病院 眼科外来
http://andonoburo.net/on/5679
講演要約
21世紀の医療には、あまり目立ちはしないが「物語論」という静かな潮流がずっと流れ続けている。日本語の「物語」は、英語のstoryやnarrativeに対応している。このうちnarrativeという英語が、最近の医療ではカタカナでそのまま使われることが増えている。物語論の考え方を応用した様々な実践がなされていて、これを一括りにして「ナラティヴ・アプローチ」とか「ナラティヴ実践」と呼んでいる。
ナラティヴ・アプローチにはきわめて多様なものが含まれるが、「物語への向き合い方」という視点で捉えれば、3つの系統に分類できる。まず、医療者が患者という「他者」の経験を、当人の文脈のなかで理解しようとする実践群がある(これを仮に「現象学的実践」と呼んでおく)。
1990年代末に、「エビデンス・ベイスト・メディスン evidence-based medicine」(文献的根拠に照らして最善の治療法を選択しようという考え方)の行き過ぎを憂慮した医師たちが提唱したのが「ナラティヴ・ベイスト・メディスンnarrative-based medicine」であったが、そこには、「医療者は専門性の枠組みの中で病気を捉えるが、病気を抱えているのは患者であり、その経験は医療者にとって容易に理解できるものではない」という問題意識があり、治療方針の選択については「疾患が患者にもたらす影響は、その当人の人生史や価値観によって左右されるのだから、医療者は文献上のデータではなく、個々の患者の人生の文脈において最善と評価できる治療・ケアを選択すべきだ」という発想の転換があった。
第2の系統は、「物語」をケアとして用いる実践群である(仮に「ケア的実践」と呼んでおく)。
これは、1970年代に心理療法の中から誕生したナラティヴ・セラピーと呼ばれる一群の実践に端を発している。そこでは、患者の「自己物語」と「認知・経験」とが矛盾することで心理的問題が生じると見なされ、治療者が患者に「自己物語の書き換え」を促すことが、ケアの目標となる。ナラティヴ・セラピーは、気分障害、発達障害、トラウマ、アディクション、摂食障害、DV等々の多岐にわたる「心の病」を抱える人たちのためのものであるが、そこに散りばめられていた斬新なアイデアは、もっと広い範囲の対象に適用できるのではないかという期待を強く抱かせた。
講演では、食事を取ったことを忘れてしまった認知症患者への声かけを考えた。認知症患者の脳は、認知機能は低下するが情動機能は維持されているとされる。そのため、食事をしたことを思い出させようとするあまり、相手の自尊感情を損なうようなコミュニケーションは望ましくない。「食事を取らなければいけない」という患者の「自己物語」を他人が無理に変更させることで、患者の脳では「否定された」という情動が働いてしまう。むしろ、「わかりました。ご飯の準備をしておきますね」等と、自尊感情に配慮した声かけをすることで、「認知・経験」との矛盾を拡大させずに、「食事を取らなければいけない」という気持ちがやわらぐのを待つ方がよい。
第3の系統が、筆者が専門的に取り組んできた、医療倫理の方法論としてのナラティヴ実践である。そこでは「倫理的問題は当事者の物語の不調和で生じる」と見なして、「対立し合う物語の調停」を試みる(仮に「調停的実践」と呼んでおく)。
講演では、意識回復が望めない脳梗塞患者に胃瘻を造設するか否かが問題になった事例を考えた。妻は「本人は延命治療をしないでほしいと言っていた」と反対し、息子は「このまま死なせるのは忍びない。打てる手があるならお願いしたい」と実施を求めた。ここにあるのは、患者との関わりや、歩んできた道のりの違いに根ざす「思い」のズレであり、このズレを「妻の物語と息子の物語の不調和」と捉えることで、それを解消するためにどんな対話をこの2人としていけばよいのかを考える道が開けてくる。例えば、妻は患者の気持ちを代弁しているように思えるが、自分自身の気持ちはどうなのかを聞いてみてはどうだろうか。息子が抱いている父親への思いには大いに共感できるが、胃瘻の効果を医学的に考えてみると、この状態の患者に「胃瘻を作らない」ことが、必ずしも「何も手を打たないこと」とは言えないように思えることを伝えてみてはどうか。
以上が講演の概略であるが、これらが眼科領域にどのように適用できるのかは、これまでほとんど考えたことがなかった。特に、ナラティヴ実践の中には視覚的なもの(紙芝居や絵本を作ったり、写真やビデオを用いたりする実践など)もあるが、これらはそのままでは適用することができない。しかし、講演後に視覚障害を持つ方から出された感想や意見をうかがうと、彼らが私の話を細部に至るまで丁寧に聞いてくれており、しかも自分の経験に照らして様々な発想を展開していることに驚かされた。視覚障害者にとっての「物語」の豊かさを感じたとともに、彼らとともに様々なナラティヴ・アプローチを試みることも、眼科の医療にとって意味があることのように思えた。
略歴
1965年長野県松本市生まれ。
早稲田大学教育学部理学科生物学専修卒業、大阪大学大学院医学研究科修士課程修了、東京大学大学院医学系研究科博士課程単位取得、博士(医学、東大)。専門は医療倫理、ナラティヴ・アプローチ(医療における物語論)など。
2011年より新潟大学医学部保健学科教授。
著書に『医療倫理学の方法 - 原則, 手順, ナラティヴ』(医学書院)、『ハンセン病 重監房の記録』(集英社)、『専門家をめざす人のための緩和医療学』(共著、南江堂)、『ナラティヴ・アプローチ』(共著、勁草書房)など。
宮坂道夫研究室ホームページ
http://www.clg.niigata-u.ac.jp/~miyasaka/
後記
宮坂道夫先生は、全国区で活躍している生命倫理の大家です。眼科領域でも臨床眼科学会で講演して頂いたり、「日本の眼科」に投稿して頂いています。
今回のお話は、「病いの物語」という演題でお話して頂きました。EBM(evidence-based medicine,根拠に基づく医療)が大流行りの今日、NBM(Narrative Based Medicine)をテーマとしたお話です。
私が理解した先生のお話は、、、物語(ナラティブ)に基づいた医療。物語とは何か?アリストテレス(BC384年 - 322年)によると、物語は「再現・シークエンス(展開)・登場人物・感情を揺さぶる」と集約できる。 NBMでは、傾聴・関係性・ケアが基本。一言でいうと、医師は医療の標準化を求めEBMに精を出す。一方、NBMは患者目線での個別化医療。以下の言葉が、印象に残りました。他者理解のNBMとケアの実践のNBM、「無知のアプローチ」、「スニーキー・プー」、問題の外在化、「人生紙芝居」
今回も、色々な角度から物事の本質を見つめる宮坂先生の世界を知り、大変勉強になりました。
宮坂先生の益々のご活躍を祈念致します。