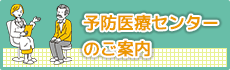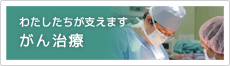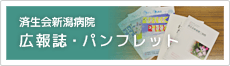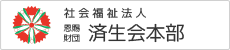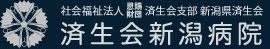眼科
報告:第224回(14‐10月)済生会新潟第二病院眼科勉強会「目の愛護デー記念講演2014」
演題:「視力では語れない眼と視覚の愛護」
講師:若倉雅登(井上眼科病院;名誉院長)
日時:平成26年10月8日(水)17:00 ~ 18:30
場所:済生会新潟第二病院 眼科外来
http://andonoburo.net/on/3301
講演要約
眼の病気と言えば、ドライアイや白内障、緑内障、加齢黄斑変性など、メディアなどで聞きなれた眼の疾患を思い起こす人が多い。だが、眼科の領域は実は非常に広い。神経眼科、心療眼科を専門として40年近く診療を続けてきた中で、快適な視覚を得るためには、眼球と脳、とりわけ高次脳機能との精緻な共同作業が必要なことを学んだ。しかも、左右眼のバランスは、その機能を発揮する上で非常に大切で、逆にアンバランスは眼精疲労の原因になるだけでなく、日常視、日常生活に甚だしい支障をもたらし、時には心の問題も惹き起こす。
眼はものを見る器官だから、一般人も眼科医も「目」といえば「視力」のことばかり考える。だが神経眼科のフィルターを通してみると、左右眼の視力がいかに良好であっても、見ることに不都合が起こる可能性のある病態が沢山あり、多くが見落とされてきたことに気付く。
快適な日常視とは、必ずしも視力や視野だけでは語れないものである。眼科で測定する視力や、視野は非常に理想的な環境で測っており、日常生活で使っている視機能、つまり実効視機能を反映しているとは限らないことに思いを致すべきである。
たとえば、「かすむ・ぼやける」といえば、一般の眼科医は眼球そのものに存在する病気を考えるが、私の視点だと、調節・輻輳、両眼視機能など高次脳機能の障害が頭に浮かぶ。「しょぼしょぼする」「眼が痛い」と言えば、普通はまず角膜や結膜、涙器などの疾患を考えるが、私は神経薬物(とくに睡眠導入剤や安定剤として多用されるベンゾジアゼピン系の薬物)の副作用や、「眼瞼痙攣」という開瞼が自在にしにくく眼は正常でもうまく使えず、それだけでなく眼や眼周囲にまぶしさや不快感が出現する脳の神経回路の故障が原因となる病気が隠れていないかと気になる。ちなみに、この眼瞼痙攣という疾患は決して珍しいものでないが、大抵ドライアイと誤診されている。
両眼で見るとものがふたつに見える「複視」には、脳内病変や、眼球を動かす脳神経や筋肉の病気を考え、多くの眼科医は脳外科などに送って脳の画像診断を試みるが、もしその患者が、日本人に多い強度近視で、かつ「遠方のものが二つに見える」のであれば、私たちのグループが見つけた「眼窩窮屈病」(Kohmoto etal:Clin.Ophthalmol5.5-11.2011,若倉:臨床眼科 67:1458-63,2013)の存在を考える
べきである。このように少し見方を変ずれば、視力検査などでは気付かない原因の視覚の不都合が、我々の周囲に少なからず潜んでいる。
さて、医師が求める医療と患者が求める医療は、同じように見えて必ずしも同じではない。医師は病を医学的に考えて治療する。医師にとって患者の自覚症状は、診断するための手がかりではあるが、患者が一番治してほしいのは日常生活に支障をきたす自覚症状であることを忘れやすい(拙著:三流になった日本の医療PHP研究所、2009)。
私は臨床に携わった約40年の間に、教科書の記載として残るだろう疾患や病態を見つけてきた。難しいことではなく、なぜ、これまで医師が気付かなかったのだろうと思うようなことばかりだ。副腎ステロイドによる中心性漿液性網脈絡症、睡眠導入剤による眼瞼痙攣の発症、眼瞼痙攣の軽症例への認識、眼窩窮屈病の存在、レーベル遺伝性視神経症では対光反射が良好であり、中心耳側(もしくは耳上側)の感度低下からはじまる臨床像の特徴を見出したことなどである。
いろいろな眼や脳の病態のために、見え方の左右差が大きすぎたり、治療をしても代償できない複視に、積極的に単眼視を導入することで、患者の辛い日々を半分程度は改善させられることにも気づいた。 見え方の左右差や複視は「耳鳴り」ならぬ「目鳴り」を発生させ、日常視が苦しく、ひいては日常生活に大きな苦痛を与えるからである。これは、これまでなぜか、どの眼科医も関心を示さず、実行されてこなかったことである。
臨床現場における私のスタンスは、①常識や教科書にとらわれず常に患者の愁訴や所見から学ぶ、②患者の実感に思いを致しながら、相手の話を傾聴し、③視力視野にとらわれず実生活での視機能(見え方や眼の使い心地)を重視するというものである。そして、④判らないことは判らないと正直にいうものの、自分はこう考えるという「見立て」も必ず添えて、患者さんとともに、治療や対策を考える。 そのことで、今日の医学では十分治せない疾患や病態に対しても「医師は患者の最大の味方」であることを少しでも実現させたいとの気持ちで、やっている。「見立て」とは随分と古めかしい言葉だが、患者医師関係をしっかり築いてゆくには必要なことである。
少しだけ自慢するのを許していただけるなら、そういう私の虚心坦懐に、目線を低くして患者の訴えに耳を傾ける姿勢でこそ、上記のような成果を得ることができたのだと思う。
今、ロービジョンという概念の中には、視力低下や視野の異常は存在するが、本日私が挙げたような両眼視や中枢性視覚障害は入ってこない。患者の立場でみると、後者のような病態も視力視野の異常をきたす疾患と同等か、それ以上に生活の質を落としている。 私はそういうものをも含めて「Visual handicap」という概念を導入したいと提案する。Visual handicapを伴う方々の眼科的、精神的ケアこそ「眼の愛護」と呼びたいのである。
略歴
若倉雅登(わかくらまさと)(2014年4月現在)
1976年3月 北里大医学部卒
1980年3月 同 大学院博士課程終了
1986年2月 グラスゴー大学シニア研究員
1991年1月 北里大医学部助教授
1999年1月 医)済安堂 井上眼科病院 副院長
2002年1月 医)済安堂 井上眼科病院 院長
2012年4月 医)済安堂 井上眼科病院 名誉院長
ほかに現在:北里大学医学部客員教授、東京大学医学部非常勤講師
日本神経眼科学会理事長、日本眼科学会評議員など
後記
毎年、10月の勉強会は「眼の愛護デー」に関したお話を眼科医にお願いしています。今回も素晴らしい講演を拝聴できました。目の病気というと視力ばかりが話題となりますが、視力が良くても不自由を感じているものも少なくありません。そうした不自由をお聞きすることは簡単なことではありません。また理解できない訴えを聞き続けることは、実は結構しんどいことです。
「医学では十分治せない疾患や病態に対しても『医師は患者の最大の味方』であることを少しでも実現させたい」との言葉には重みを感じます。
今回の勉強会で、一番勉強になったのは誰でもない、実は私ではなかったかと思って
います。